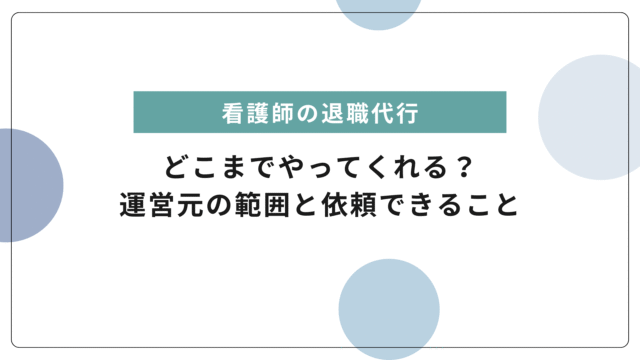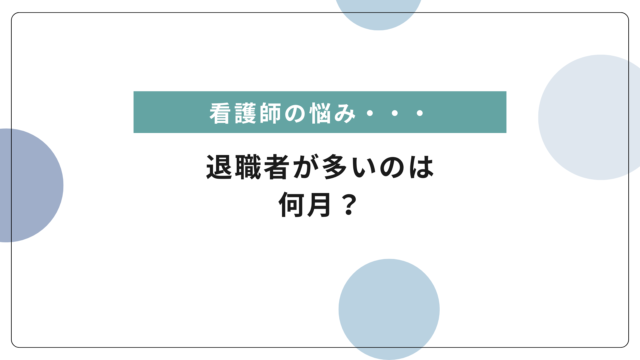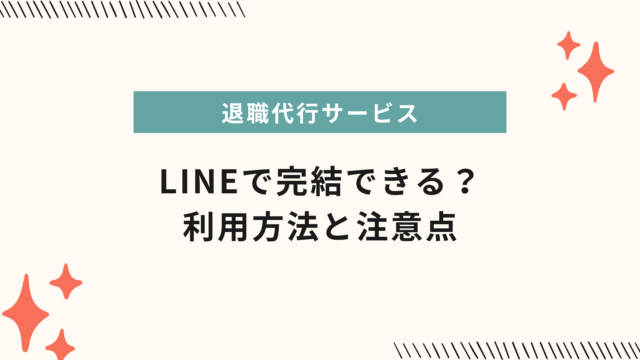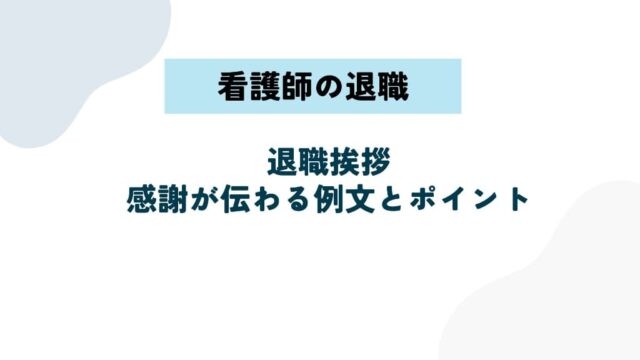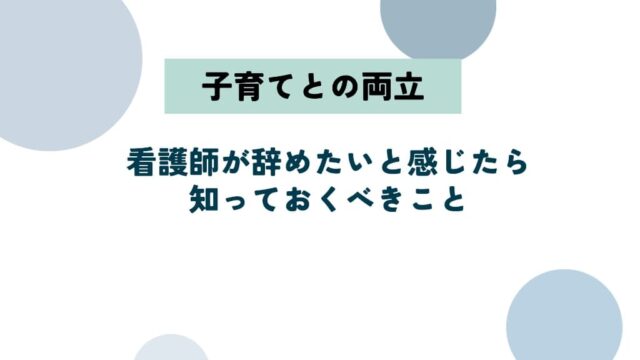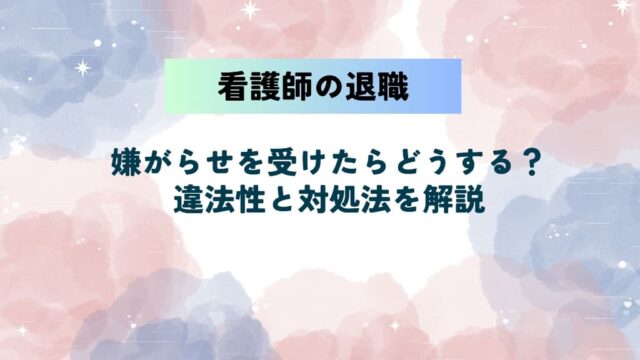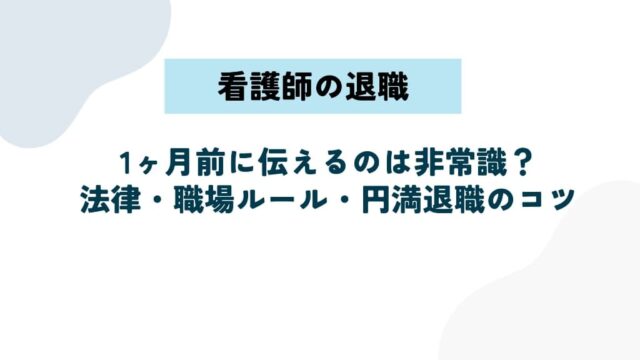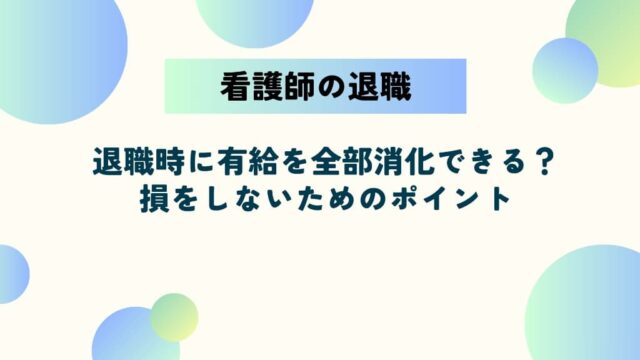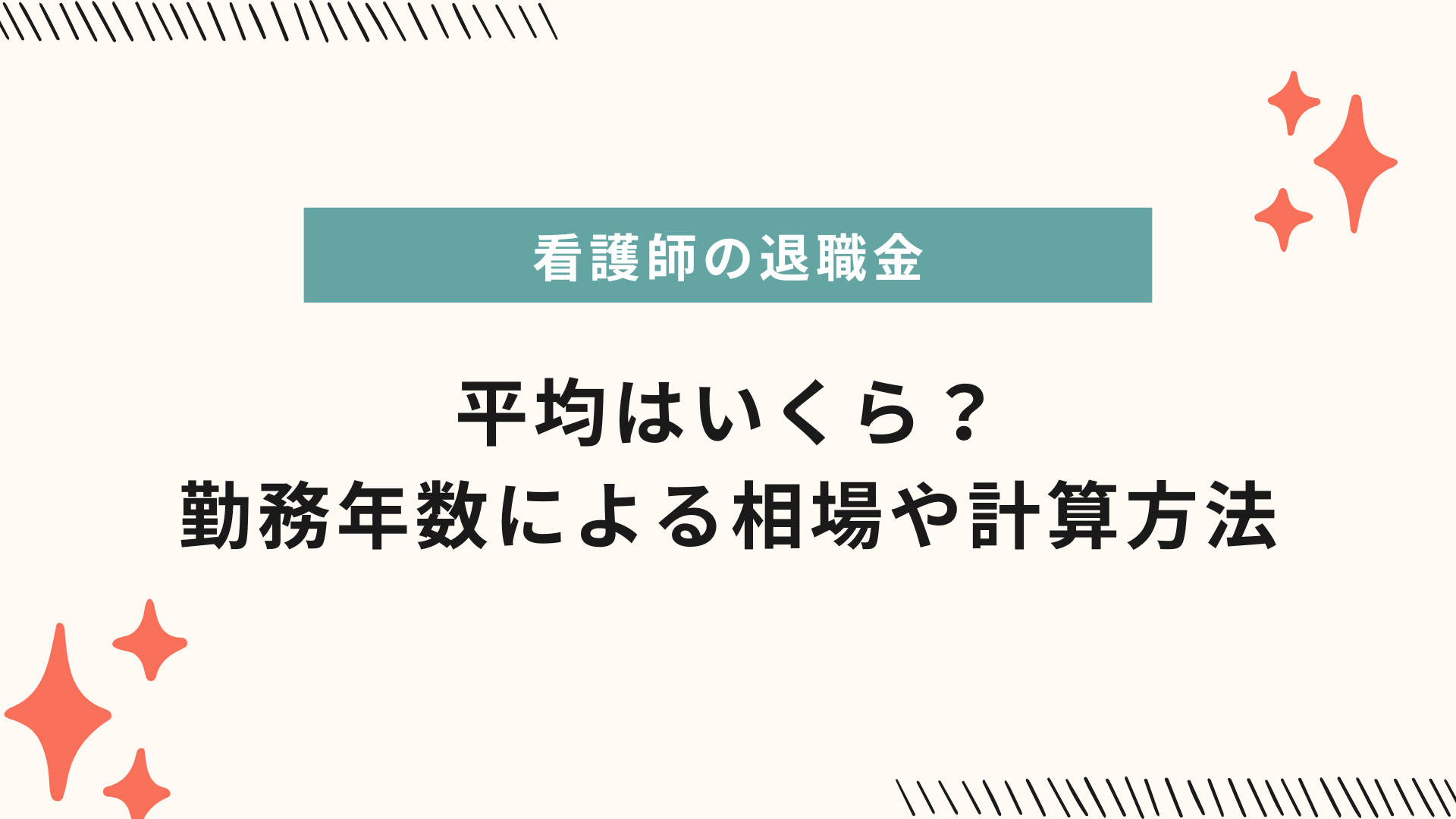
看護師の退職金は、長年の労働に対する報酬であり、退職を考えている人にとって最も気になるものではないでしょうか。
退職金は、看護師としての長年の貢献に対する感謝の証であり、次のキャリアステップへの支援でもあります。
しかし、病院や医療機関によって退職金制度は大きく異なるため、自分の働く環境における退職金の仕組みを理解することは非常に重要です。
この記事では、看護師の退職金について、以下のポイントを詳しく解説します。
- 勤務年数別の退職金相場
- 具体的な退職金の計算方法
- 退職金に影響する要因
- 退職金を増やすためのポイント
看護師としてのキャリアを考える上で、退職金は重要な検討要素の一つです。まずは、ご自身の職場でいくらの退職金がもらえるのか、しっかりと把握しましょう。
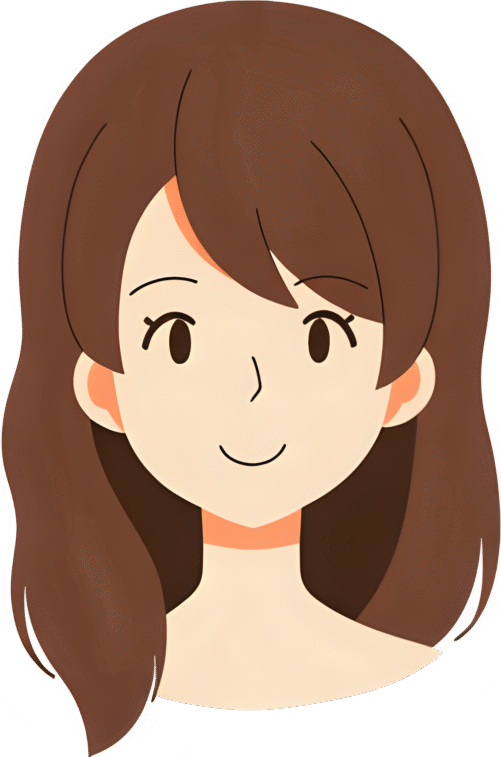
ちなみに私は、大学病院の看護師4年目を終えて退職し、退職金は38万円でした・・
看護師の退職金制度の基本

看護師の退職金制度について、まずは基本的なポイントを押さえておきましょう。
- 退職金とは何か
- 看護師の退職金制度の特徴
- 退職金の支給条件
3つのポイントに沿って解説します。
退職金とは何か
退職金は、長年勤務した従業員に対して、退職時に支払われる一時金のことです。
これは労働者の長年の貢献に対する感謝の意を表し、退職後の生活を支援する役割を果たします。
退職金は法律で義務付けられているものではなく、各企業や組織が独自に制度を設けているため、自分の職場の規則について確認することが大切です。
看護師の退職金制度の特徴
看護師の退職金制度は、一般企業とは異なる特徴を持っています。
多くの医療機関では、看護師の専門性と長期勤続を重視する傾向があり、それが退職金制度にも反映されています。
たとえば、勤続年数に応じて退職金が大きく増加する仕組みや、資格や役職に応じて退職金が上乗せされる制度などが一般的です。
また、公立病院と私立病院では退職金制度が大きく異なることも特徴の一つです。
公立病院では比較的手厚い退職金制度が設けられていることが多いのに対し、私立病院では病院の規模や経営状況によって制度が大きく異なります。
退職金の支給条件
看護師の退職金の支給条件は、勤務先によって様々です。
一般的には、一定期間(例えば3年や5年)以上勤務することが支給の条件となっています。また、退職理由によっても支給額が変わることがあります。
中途採用者の場合、前職の勤務年数が通算されるかどうかも重要なポイントです。
一部の医療機関では、看護師としての総勤務年数から退職金を計算する制度を採用しています。これは、キャリアの途中で転職をした看護師にとって有利な条件となっています。
看護師の退職金の平均額
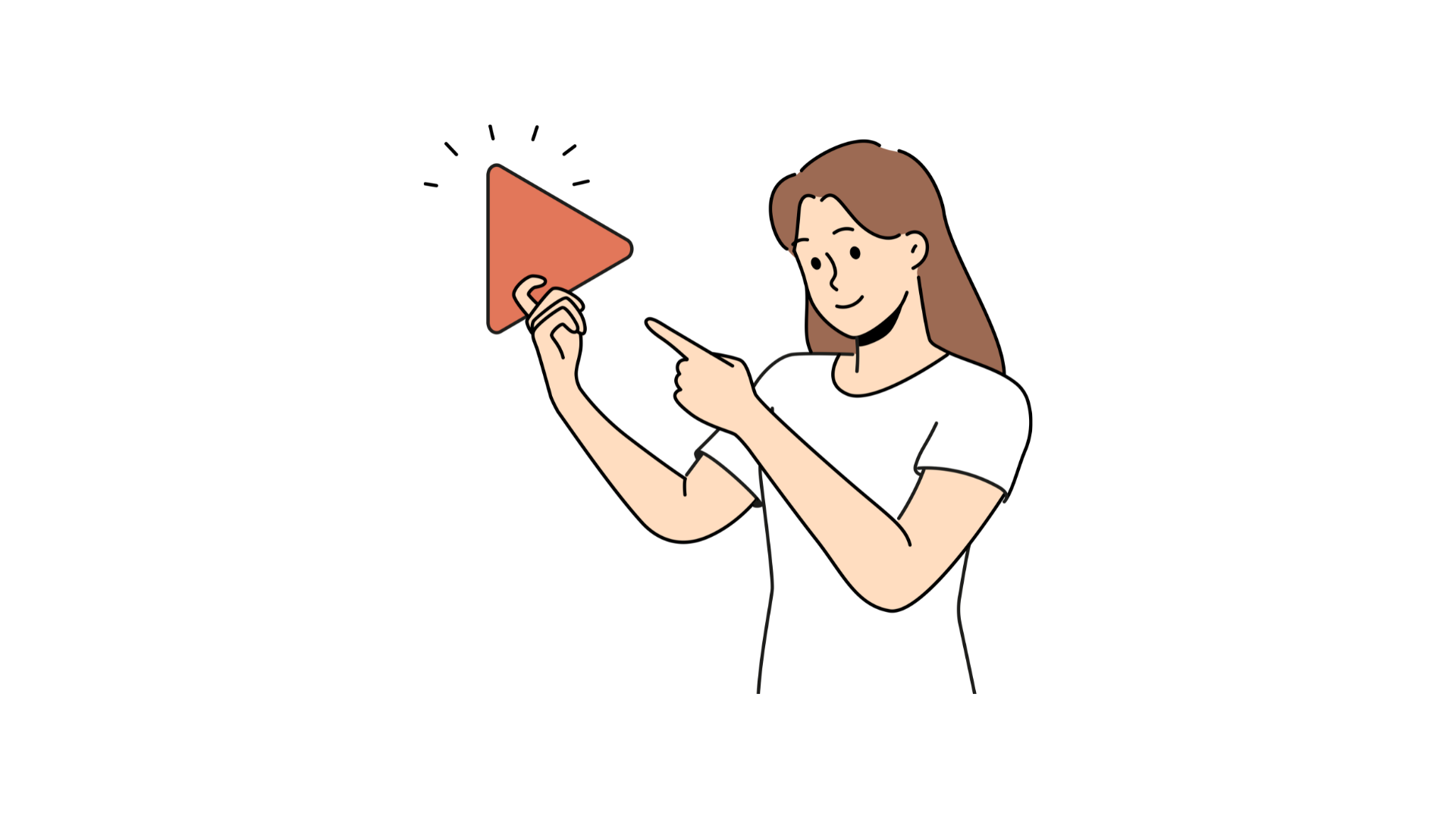
看護師の退職金は、勤務先や地域によって差があります。ここでは、基本的な相場や勤務先・地域別の平均額について解説します。
- 平均額
- 勤務先による違い(国立、公立、私立)
- 地域による差異
それぞれ詳しく見ていきましょう。
看護師の退職金の平均額・相場
看護師の退職金は、勤務先や勤続年数によって大きく異なりますが、定年時の退職金は1,000万円以下~2,000万円程度といわれています。
例えば、勤続10年で250万~300万円、勤続30年で800万~900万円程度が支給されるケースが一般的です。
特に退職の場合、国立病院や公立病院では1,000万円以上の高額な退職金をもらえるケースもあります。
ただし、退職金制度が全ての医療機関に設けられているわけではありません。
一部の私立病院や小規模クリニックでは、退職金が支給されない場合もありますので、自分の勤務先の制度を事前に確認することが重要です。
勤務先による違い(国立、公立、私立)
看護師の退職金は、勤務先の種類によって大きく異なります。以下にその特徴を解説します。
国立病院
国立病院に勤務する看護師の退職金は、定年時で約1,800万円が相場とされています。
これは、かつて準公務員として認識されていた経緯から、高水準の退職金制度が維持されているためです。
公立病院
そのため、都道府県立病院では約1,400万円、市町村立病院では約1,800万円、政令指定都市の病院では約1,900万円と高額な水準となっていることが一般的です。
私立病院
私立病院の場合、退職金は施設ごとに大きく異なります。
相場は800万〜2,000万円ですが、小規模なクリニックや経営状況が厳しい施設では退職金制度自体がない場合もあります。
また、美容クリニックなどの一部の施設では、高額な退職金を支給するケースも見られます。
地域による差異
看護師の退職金には地域差もあります。これは主に、医療機関の情勢や地域経済の影響を受けるためです。
都市部では、大規模な医療機関や一時的に余裕のある自治体が多いため、高水準の退職金を受け取れる傾向があります。例えば、東京や大阪などの政令指定都市では、公立病院勤務の場合に約1,900万円という高額な退職金が支給されることがあります。
また、一部地域では経営難から地方公務員として働く看護師でも額が減額されるケースもあるでしょう。
このように、看護師の退職金は勤務先だけでなく地域によっても大きく異なるため、自分が働いている地域や施設の特性をしっかりと考えることが重要です。
特に転職を際には、この点を考慮することで将来の収入計画をより明確にできます。
勤務年数別の退職金相場
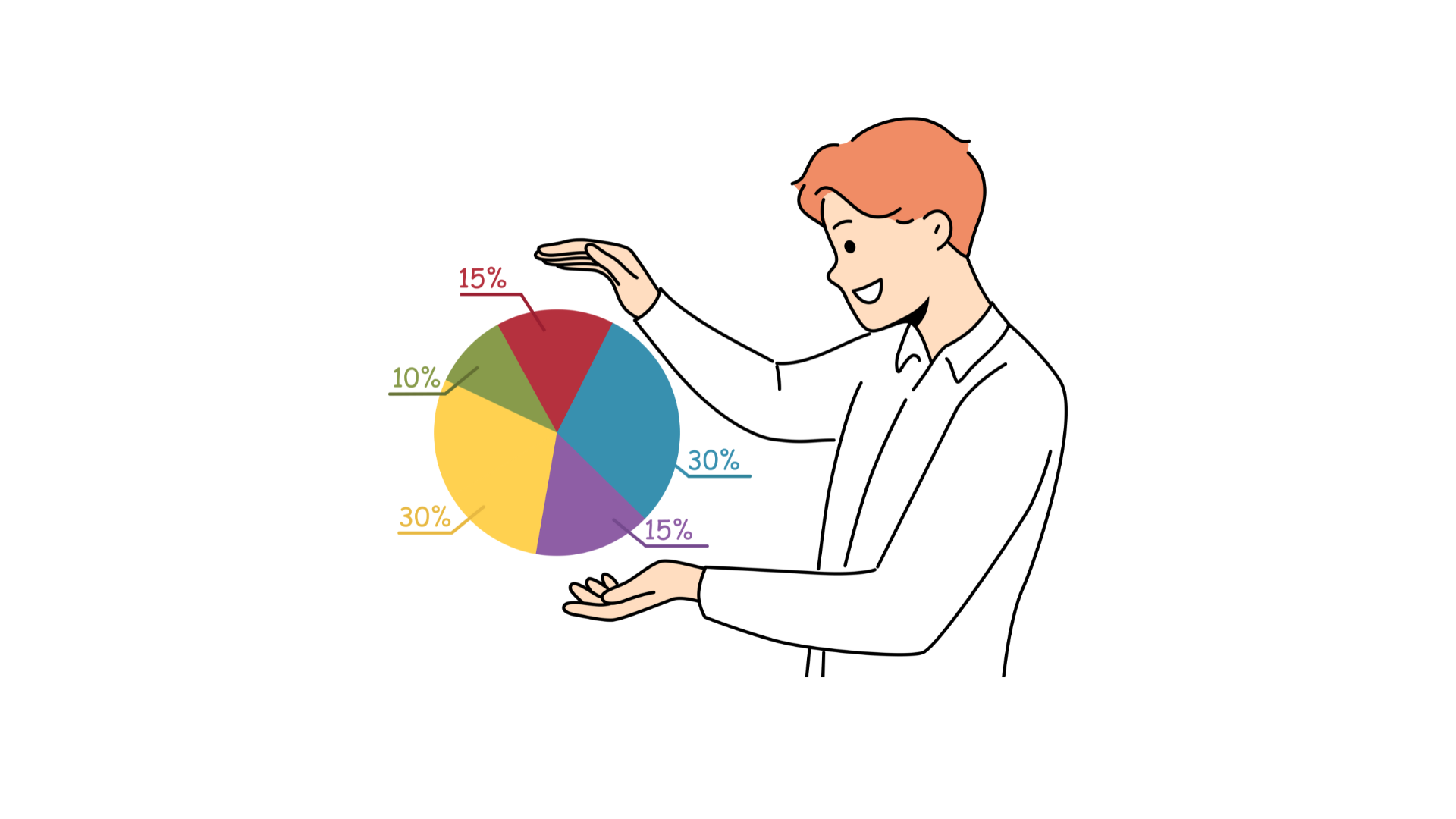
看護師の退職金は、勤務年数に大きく左右されます。
ここでは、勤務年数別の退職金相場について詳しくみていきましょう。
- 5年勤務の場合
- 10年勤務の場合
- 20年勤務の場合
- 30年勤務の場合
- 定年退職の場合
5年勤務の場合
5年という勤務期間は、多くの医療機関で退職金の支給対象となる当面の年数です。
この期間での退職金相場は、およそ50万円程度となっています。
公立病院では、5年勤務で約100万円程度150万円程度の退職が支給されることが多い一方で、私立病院では制度によってばらつきがあり、50万円程度から100万円程度まで幅広い範囲で設定されています。
5年未満で退職する場合は退職金が支払われないケースも多く、注意が必要です。
10年勤務の場合
10年勤務になると、退職金の額は大きく上昇します。一般的な相場としては、200万円程度です。
公立病院では、10年勤務で約300万円400万円の退職金が支給されるケースが多くみられます。私立病院の場合は、200万まで300万円程度が一般的ですが、病院の規模や経営状況によっては400万円を超えることもあります。
10年目の看護師の多くは、自身のキャリアアップや転職を考える時期でもあります。退職金の額は、転職の判断材料の一つとなるでしょう。
20年勤務の場合
20年という少し勤務した場合、退職金はさらに増加します。一般的な相場は600万程度です。
公立病院では、20年勤務で約800万円で1,000万円の退職が支給されることが多くみられます。
私立病院の場合は、600万とか800万円程度が一般的ですが、大規模病院や経営状況の良い病院では1,000万円を超えることもあるでしょう。
この時期になると、退職金の額に役職資格による上乗せが反映されることも多くなります。
30年勤務の場合
30年以上の長期勤務になると、退職金は非常に高額になります。
公立病院では、30年勤務で約1,300万円1,500万円の退職金が支給されることが多くみられます。私立病院の場合は、1,000万〜1,300万円程度が一般的ですが、病院の規模や経営状況、役職によっては1,500万円を超えることもあります。
この時期は、多くの看護師が管理職に就いていることが多く、それに応じて退職金も増額します。
定年退職の場合
退職時の退職金は、看護師のキャリアの集合体ともいえる金額になります。
一般的な相場は1,500万程度で2,500万円程度ですが、3,000万円を超えるケースもあります。
公立病院では、退職退職時に約2,000万円〜2,500万円の退職金が支給されることが多いです。国立病院機構ではさらに高額で、2,500万〜3,000万円程度になることもあります。私立病院の場合は、1,500万〜2,000万円程度が一般的ですが、大規模病院や経営状況の良い病院では2,500万円を超えることもあります。
退職時の退職金は、これまでのキャリアの総決算となるため、役職や資格、勤務態度などが総合的に評価され、金額に反映されます。
また、この時期の退職金は老後の生活設計に大きく影響するため、計画的な資産運用が重要です。
看護師の退職金計算方法
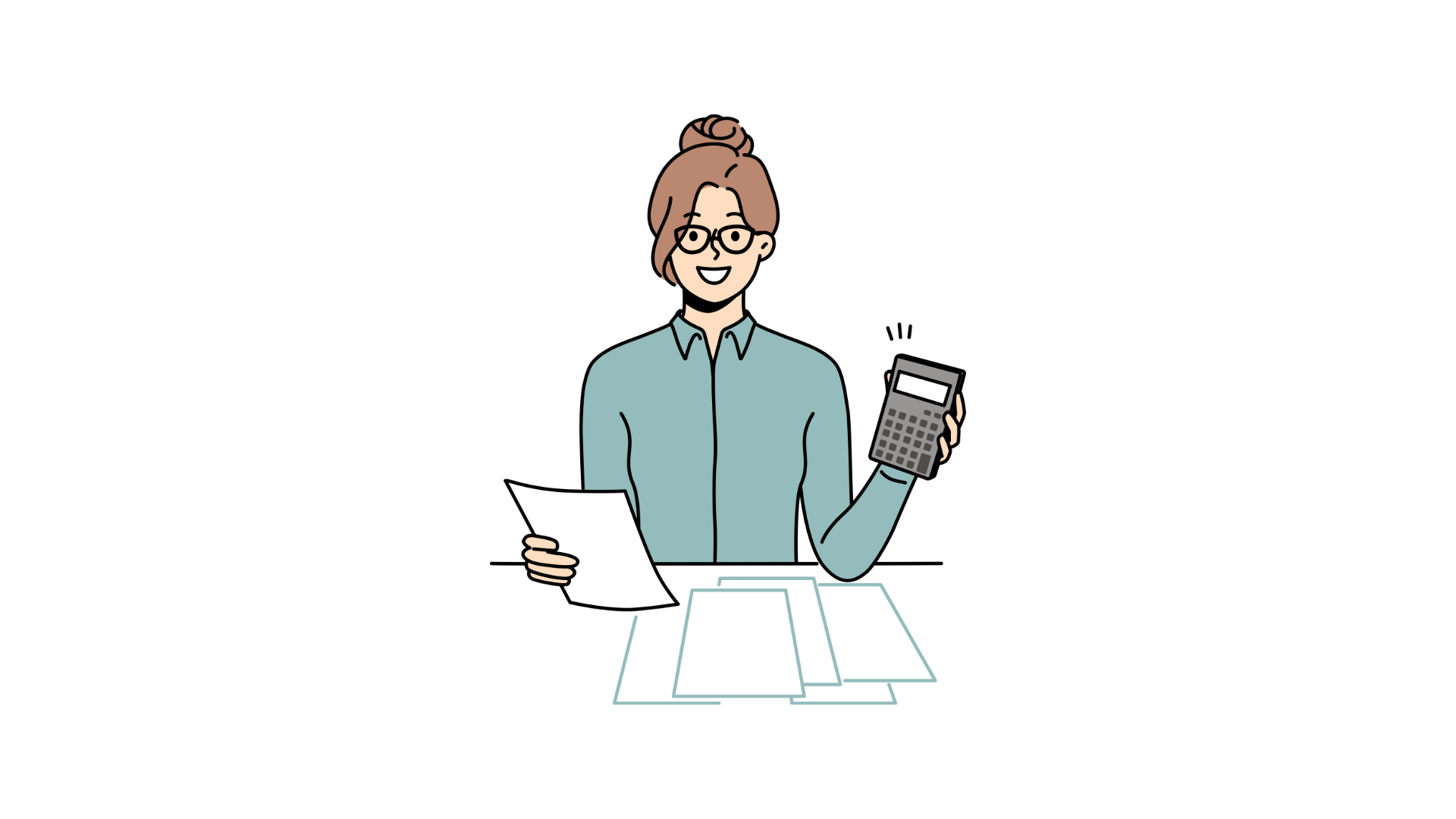
看護師の退職金の計算方法は、勤務先によって異なりますが、一般的には以下の4つの方式が用いられています。
- 基本給ベースの計算方法
- 固定金ベースの計算方法
- 勤続年数ベースの計算方法
- 功績倍率ベースの計算方法
- 具体的な計算例
それぞれの特徴と計算方法を詳しく見ていきましょう。
基本給ベースの計算方法
基本給ベースの計算方法は、最終月の基本給を基準に退職金を算出する方式です。
この方法は多くの医療機関で採用されており、以下の公式で計算されます。
退職金 =基本給 × 給与倍率 × 勤続年数
支給倍率は通常0.5から2.0の間で設定され、継続勤年数や退職理由によって変動します。
例えば、自己都合退職の場合は低いめの倍率が、退職退職の場合は高い倍率が適用されることが多くみられます。
この方式のメリットは、長年の昇給が退職金に反映されることです。
固定金ベースの計算方法
固定金ベースの計算方法は、勤続年数に応じて定額を支給する方式です。
この方法は、計算が簡単で分かりやすいという特徴があります。
退職金 = 固定金額 × 勤続年数
固定金額は医療機関によって異なりますが、例えば1年あたり10万円と設定されている場合、10年勤務で100万円の退職金が支給されることになります。
この方式のメリットは、勤務年数に応じて確実に退職金が増えていくことです。
ただし、昇給や役職の変更が退職金に反映されないため、長期勤続者や管理職にとっては不利な場合があります。
勤続年数ベースの計算方法
継続勤年数ベースの計算方法は、継続勤年数に応じて支給額を段階的に増やしていく方式です。
この方法は、長期勤続を奨励する意味が強いことが特徴です。
例えば、以下のような設定が考えられます。
- 5年未満:年10万円
- 5年以上10年未満:年15万円
- 10年以上20年未満:年20万円
- 20年以上:年25万円
この場合、15年勤務した看護師の退職金は、(5×10万)+(5×15万)+(5×20万)=225万円となります。
この方法のメリットは、長期勤続者にとって有利な点です。
代わりに、中途採用者や比較的短期間で退職する看護師にとっては不利になる可能性があります。
功績倍率ベースの計算方法
功績倍率ベースの計算方法は、勤続年数や役職、資格などを総合的に評価して退職金を算出する方式です。
この方法は、個人の貢献度を反映させやすいという特徴があります。
退職金 =基本給 × 勤続年数×功績倍率
功績率は、勤続年数や役職、特別な功績などによって決定されます。
例えば、以下のような設定が考えられます。
- 基本倍率:勤続年数×0.05
- 役職手当:主任+0.5、師長+1.0、部長+1.5
- 資格加算:専門看護師+0.5、認定看護師+0.3
この方法のメリットは、個人の努力や成果が退職金に反映されやすい点です。
具体的な計算例
ここでは、基本給ベースの計算方法を用いて、具体的な計算例を示します。
例:Aさん(45歳、看護師長、勤続20年、基本給35万円)が退職前に自己都合する退職の場合
- 基本給:35万円
- 支給倍率:1.5(自己都合退職のため)
- 勤続年数:20年
- 退職金 = 35万円 × 1.5 × 20年 = 1,050万円
この例では、Aさんの退職金は1,050万円と計算されます。
なお、実際の退職金は医療機関の規定や退職時の状況によって変動する可能性があります。
また、同じAさんが退職する場合、給与倍率が2.0に上がると仮定すると、退職金は以下のように計算されます。
- 基本給:35万円
- 支給倍率:2.0
- 勤続年数:20年
- 退職金 = 35万円 × 2.0 × 20年 = 1,400万円
このように、退職理由によって支給率が変わることで、退職金額に大きな差が生じる可能性があります。
看護師の皆さんは、自分の勤務先の退職金制度をよく理解し、キャリアプランニングに活用することが重要です。
また、退職金の計算方法や金額について不明な点がある場合は、人事部門に確認することをおすすめします。
看護師の退職金に影響を与える要因

看護師の退職金は、単純に継続勤年数だけで決まるわけではありません。
様々な課題が複雑に絡み合って、最終的な退職金額が決定されます。
- 勤務先の規模や種類
- 退職理由(自己都合vs会社都合)
- 役職や資格
ここでは、退職金に大きな影響を考慮して主な課題について詳しく解説します。
勤務先の規模や種類
勤務先の規模や種類は、退職金の額に大きな影響を与えます。
一般的に、大規模な病院や公立・国立の医療機関では、比較的高額な退職金が支給される傾向にあります。
大規模病院では、安定した経営基盤を背景に、充実した福利厚生制度として手厚い退職金制度を設けていることが多いのです。
例えば、500床以上の大規模病院では、同じ勤続年数でも中小規模の病院と比べて、1.5倍から2倍程度の退職金が支給されるケースもあります。
また、公立・国立の医療機関では、地方公務員や国家公務員に準じた退職金制度が適用されることが多く、私立病院と比較して高額になる傾向があります。
例えば、20年勤続の看護師の場合、公立病院では約1,000万円の退職金が支給されるのに対して、同規模の私立病院では600万程度になることもあるでしょう。
一方、小規模なクリニックや介護施設では、退職金制度自体が存在しない、あるいは存在しても金額が低く設定されていることがあります。
退職理由(自己都合vs会社都合)
退職理由も退職金額に大きく影響します。
一般的に、自己都合退職の場合は会社都合退職や退職退職と比べて、退職金が減額されることがほとんどです。
自己都合退職の場合、退職金の支給倍率が低く設定されています。基本給の1.0倍から1.5倍程度の支給倍率が適用されることが多いのが特徴です。
一方、会社都合退職(病院の閉鎖や人員整理など)や退職退職の場合は、より高い給与倍率が適用されます。基本給の2.0倍から2.5倍程度の給与倍率が設定されています。
具体的な例として、
【基本30万円、勤続20年の看護師が退職する場合】
・自己都合給退職では900万円(30万円×1.5倍×20年)程度
・会社退職退職では1,500万円(30万円×2.5倍×20年)程度
になる可能性があります。
役職や資格
看護師の場合、役職や取得している資格も退職金額に影響を与えます。
多くの医療機関では、役職手当や資格手当を退職金の計算基礎に含めたり、特別手当を設けたりしています。
例えば、看護師長や副看護部長などの管理職に就いている場合、基本の退職金に加えて役職手当が適用される場合があります。
また、専門看護師や認定看護師などの高い資格を持っている場合も、退職金に反映されることがあるでしょう。
資格に応じて基本給や諸手当が高く設定されていることで間接的に退職金が増額されたり、直接的に退職金の計算時に加算されたりします。
例えば、ある医療機関では、専門看護師の資格保有者に対して退職金を5%増額する制度を設けています。
20年勤続で1,000万円の退職金が支給される場合、この制度により50万円の上に乗せられます。
このように、看護師の退職金は様々な課題によって変動します。自身のキャリアプランを考える際には、これらの時間を総合的に考えて、長期的な視点で判断することが重要です。
また、具体的な退職金制度や金額については、勤務先の人事部門に確認することをおすすめします。
退職金の受け取り方やタイミング

看護師の退職金は、受け取り方やタイミングによって大きく3つのパターンがあります。
- 退職してすぐもらえる「退職一時金」
- 定年後に分割でもらえる「退職年金」
- 給与に含まれている「退職金前払い」
それぞれの特徴と注意点について詳しく見ていきましょう。
退職してすぐもらえる「退職一時金」
退職一時金は、最も一般的な退職金の受け取り方です。退職後に一括で支給されます。
多くの場合、退職月の翌月か翌々月に支給されることが多いですが、医療機関によっては退職時に即時支給されるケースもあります。
退職一時金のメリットは、まとまった資金を一度に受け止められることです。これにより、退職後の生活設計や新たな挑戦のための資金として活用しやすくなります。
例えば、転職のための学び直しや、起業資金として活用することが可能でしょう。
特に、退職金が高額な場合は、退職金の権利を超えた部分に対しては、税金対策を考える必要があります。また、一時金で受け取った場合、計画的な資金管理が求められます。
特に、退職後の長期的な生活設計を考える場合は、資産運用や使い方について慎重に検討しましょう。
将来分割でもらえる「退職年金」
退職年金は、退職金を一定期間分割して受け取る方式です。
主に退職者を対象としており、毎月または年に数回に分けて支給されます。
支給期間は通常5年から20年程度で、医療機関によって異なります。
退職年金のメリットは、定期的な収入が得られることで、退職後の生活の安定につながるポイントです。
特に、公的年金だけでは生活費が足りない場合に、補完的な役割を果たします。
デメリットとしては、インフレーションによる実質的な価値の低下や、医療機関の経営状況の変化によって支給が不安定になるリスクがあります。
また、急な出費が必要になった場合には、まとまった資金を用意しにくいという面もあります。
給与に含まれている「退職金前払い」
退職金前払い制度は、退職金の一部または全部を毎月の給与に上乗せして支給する方式です。
この制度を採用している医療機関では、退職時の一時金が少なくなる、または無くなる代わりに、毎月の給与が高くなります。
メリットは、現役時代の収入が増えることで、生活水準の向上や資産形成時代の機会が得られることです。
特に、若い世代の看護師にとっては、住宅ローンの返済や子育て費用など、現在の生活に必要な資金を確保しやすくなるでしょう。
デメリットは、毎月の給与が増えることで、その分の税金や社会保険料も増加することです。さらに、転職時に不利になる可能性もあります。
看護師の皆さんは、ご自身のライフプランや将来の目標に合わせて、これらの受け取り方を選択することが重要です。
また、医療機関によって制度が異なるため、入職時や制度変更の際には必ず詳細を確認し、しっかりと保管することをおすすめします。
退職金制度の最新動向
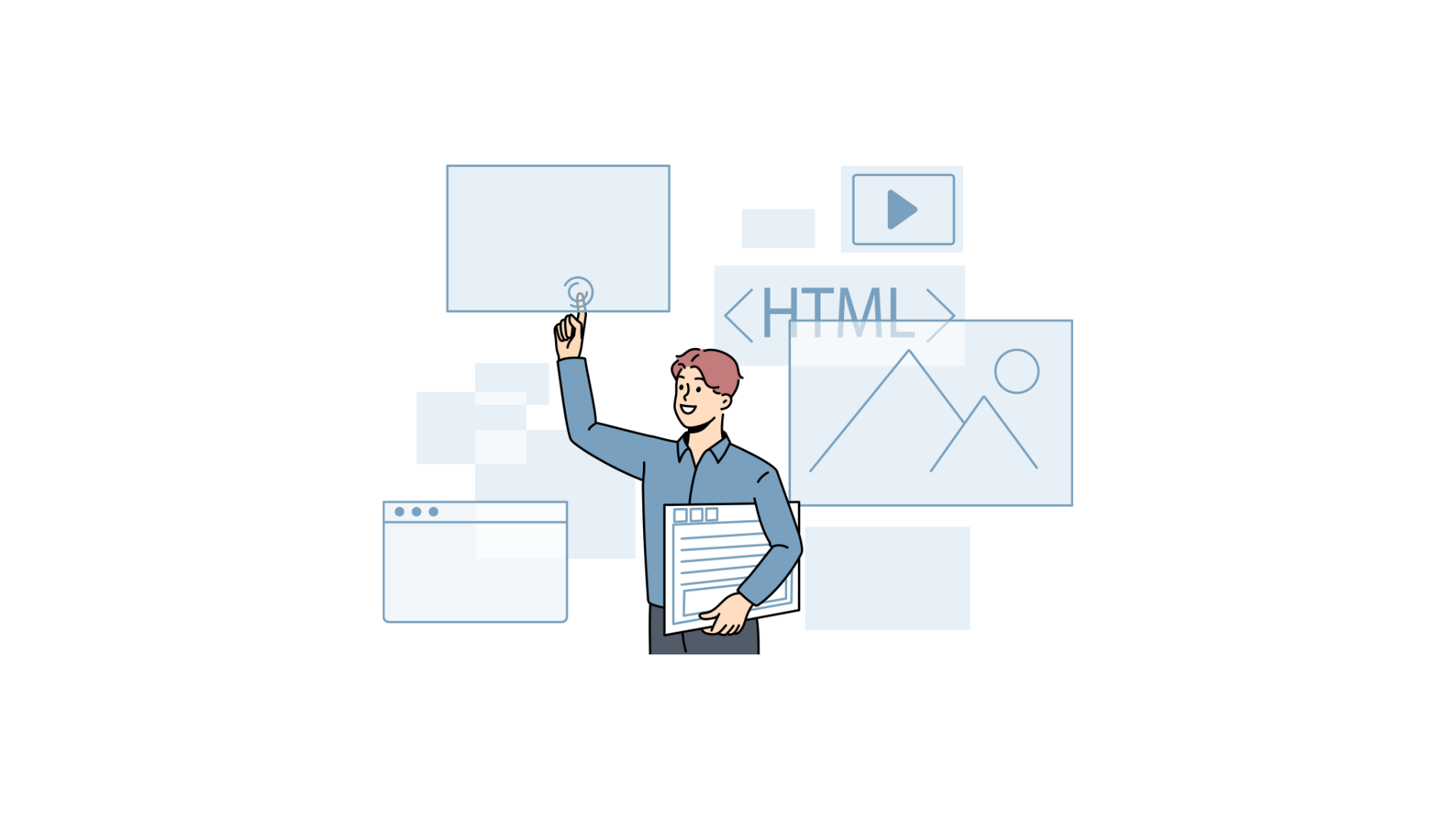
退職金制度は、年々その動向が変わっているのが現状です。ここでは、以下の2点について詳しく解説します。
- 退職金制度の変化
- 確定拠出年金への移行傾向
退職金制度の変化
看護師の退職金制度は、大きな変化を迎えています。従来の一時金支給型から、より柔軟な制度への移行が進んでいるのです。
多くの医療機関では、スタッフの多様なニーズに対応するため、複数の選択肢を用意する傾向にあります。
例えば、一部の病院では退職金の一部を毎月の給与に上乗せする「退職金前払い制度」を導入しています。
これにより、若手看護師の現金流動性を高め、生活設計の自由度を上げられるようになりました。
また、退職金の一部を資格取得研修支援や費用に充てている医療機関も増えています。
これは看護師のキャリア発展を支援し、併せて病院の人材育成にも取り組んでいることを表しているのです。
確定拠出年金への移行傾向
確定拠出年金(DC)への移行も、看護師の退職金制度における重要な傾向です。
DCは、個人が自己責任で運用する年金制度で、転職時の資産移動が容易という特徴があります。
多くの医療機関が、従来の退職一時金や確定給付金の一部または全部をDCに移行しています。
この背景には、医療機関の負担軽減や、看護師の転職増加に対応する措置があります。
ただし、DCへの完全移行には課題もあります。運用リスクが個人に移るため、金融リテラシー教育の必要性が暫定的にあることです。
そのため、多くの病院では段階的な移行や、従来型制度との併用を選択しています。
このように、看護師の退職金制度は、個人のニーズと医療機関の経営状況のバランスを取りながら、より柔軟で持続可能な形を目指して進化を続けています。
退職金を増やすためのポイント

退職金を多くもらって退職したいと考える看護師は多いでしょう。
退職金を増やすためには、以下のようにいくつかのポイントがあります。
- 長期勤続のメリット
- スキルアップの重要性
- 転職時の注意点
一つずつ詳しく解説します。
長期勤続のメリット
看護師の退職金に関して、長期勤続は非常に重要な要素です。
多くの医療機関では、勤続年数に応じて退職金の支給率が上昇する仕組みを採用しています。
長期勤続のもう一つのメリットは、役職への昇進機会が増えることです。
看護師長や副看護部長などの管理職に就くと、退職金の基本額や支給率が大幅に上昇することが一般的です。
そのため、同じ勤続年数でも、役職の任で退職金に大きな差が生じる可能性があります。
スキルアップの重要性
スキルアップは、退職金を増額するために非常に効果的な戦略です。
専門看護師や認定看護師などの高い資格を取得することで、基本給や諸手当が増加し、結果として退職金の評価基礎額が上がります。
また、多くの医療機関では、特定の資格保有者に対して退職金の増額や特別手当を行う制度を設けています。
例えば、専門看護師資格保有者に対して退職金を10%増額するような手当です。
このような制度を活用することで、退職金を大幅に増やせるようになるでしょう。
転職時の注意点
転職は、キャリアアップや労働環境の改善のために有効な手段ですが、退職金の観点からは慎重に検討する必要があります。
多くの医療機関では、勤続年数に応じて退職金が逓増する仕組みを採用しているため、頻繁な転職は退職金の減少につながる可能性があります。
ただし、転職先の選択では、退職金が増えるチャンスになるのも事実です。
例えば、退職金制度が充実している大規模病院や公立病院への転職は、長期的に見て退職金の増加につながる可能性があります。
また、転職の際には前職の勤続年数が続くかどうかを必ず確認しましょう。
退職金を増やすためには、長期的な視点でキャリアプランを立て、スキルアップと勤続年数のバランスをとりながら、戦略的に行動することが重要です。
看護師のキャリアステージ別退職金ガイド!知っておくべき退職金の平均相場まとめ
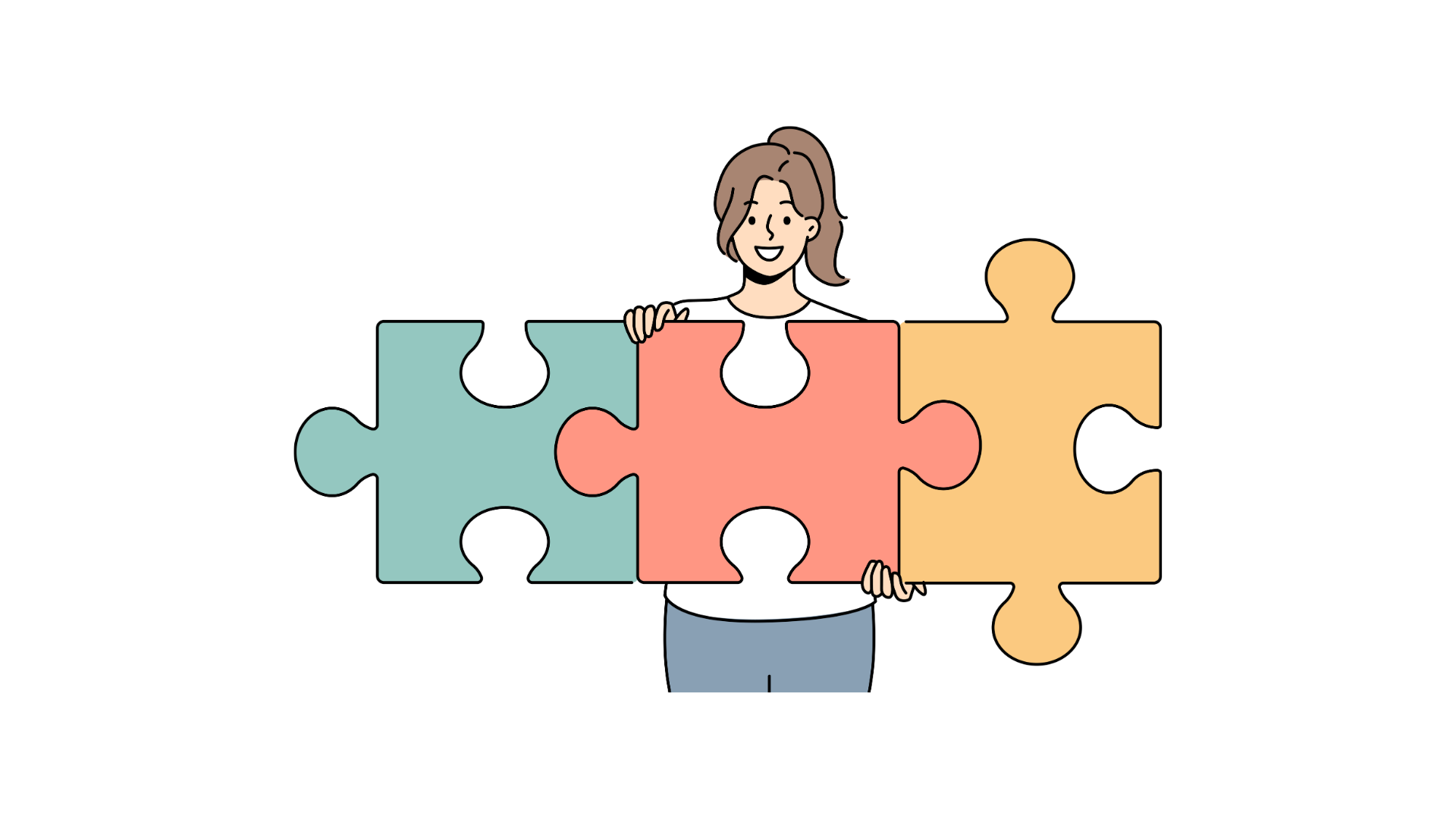
看護師の退職金は、勤務先の種類や勤続年数、役職、資格など、多様な課題によって大きく変動します。
平均的な退職金は5年勤務で100万円、10年で300万円、20年で800万円、退職時には2,000万円前後です。
看護師が退職金を最大化するためには、長期継続とスキルアップが鍵となります。専門看護師や認定看護師などの資格取得、管理職への昇進は退職金増額につながるでしょう。
また、退職金の受け取り方法も一時金、年金、前払いなど複数の選択肢があり、個人のライフプランに合わせて選択することが重要です。
最終的には、自分のキャリアデザインを意識しながら、退職金制度を理解し、戦略的にキャリアを形成していきましょう。
Wrote this article この記事を書いた人
あゆ
元ナース・保健師のあゆ。 元看護師・保健師で、転職5回を経て現在はフリーランスとして活動中! 看護師として働く中で、悩み続けて1年かけて退職した経験があります。その過程で、退職を切り出す難しさや、退職後のキャリアへの不安を痛感しました。 『ナースの退職お悩み相談室』では、退職を考える看護師の方々に役立つ情報や、退職代行サービスの活用法、退職後のキャリアプランなどを発信しています。皆さんが一歩踏み出すお手伝いができれば嬉しいです。