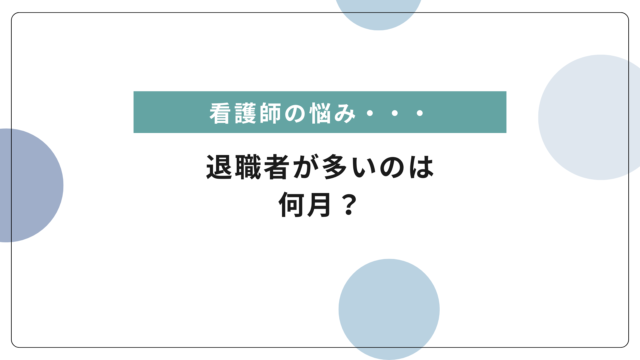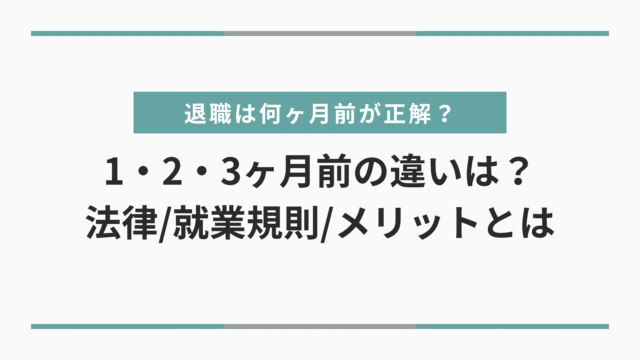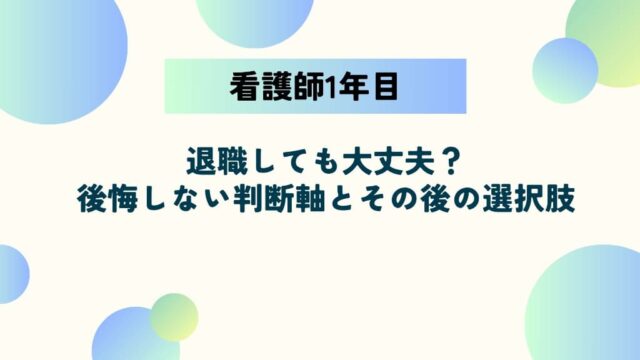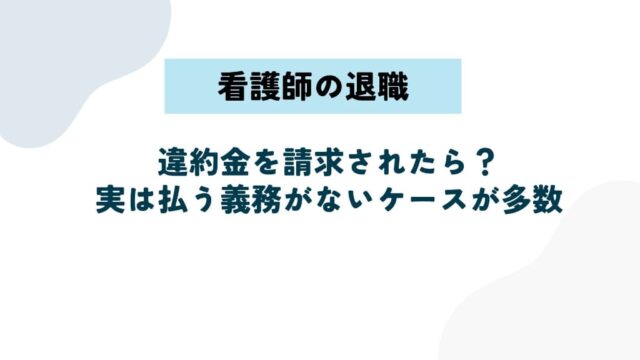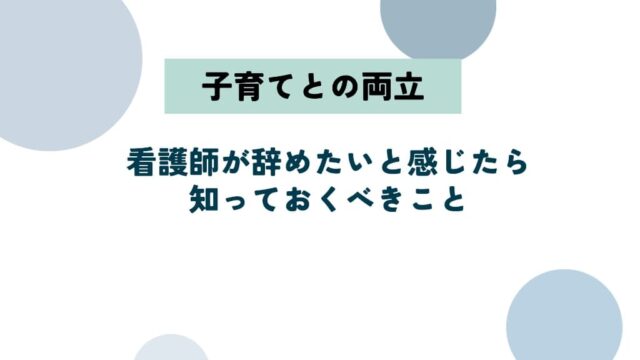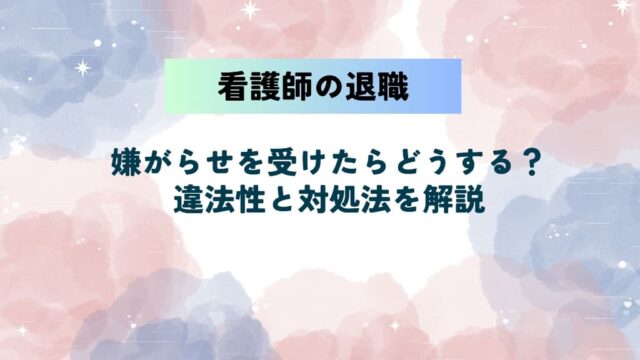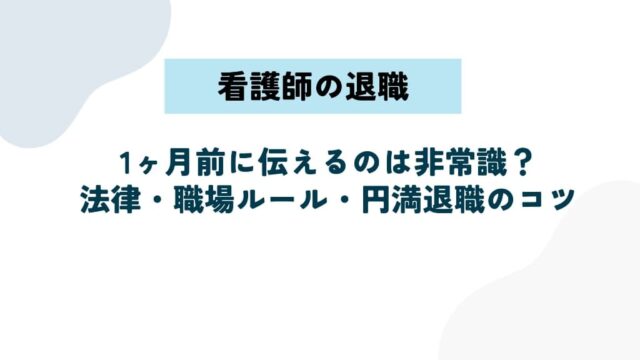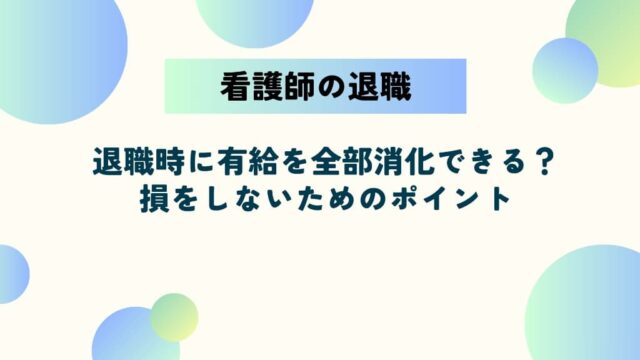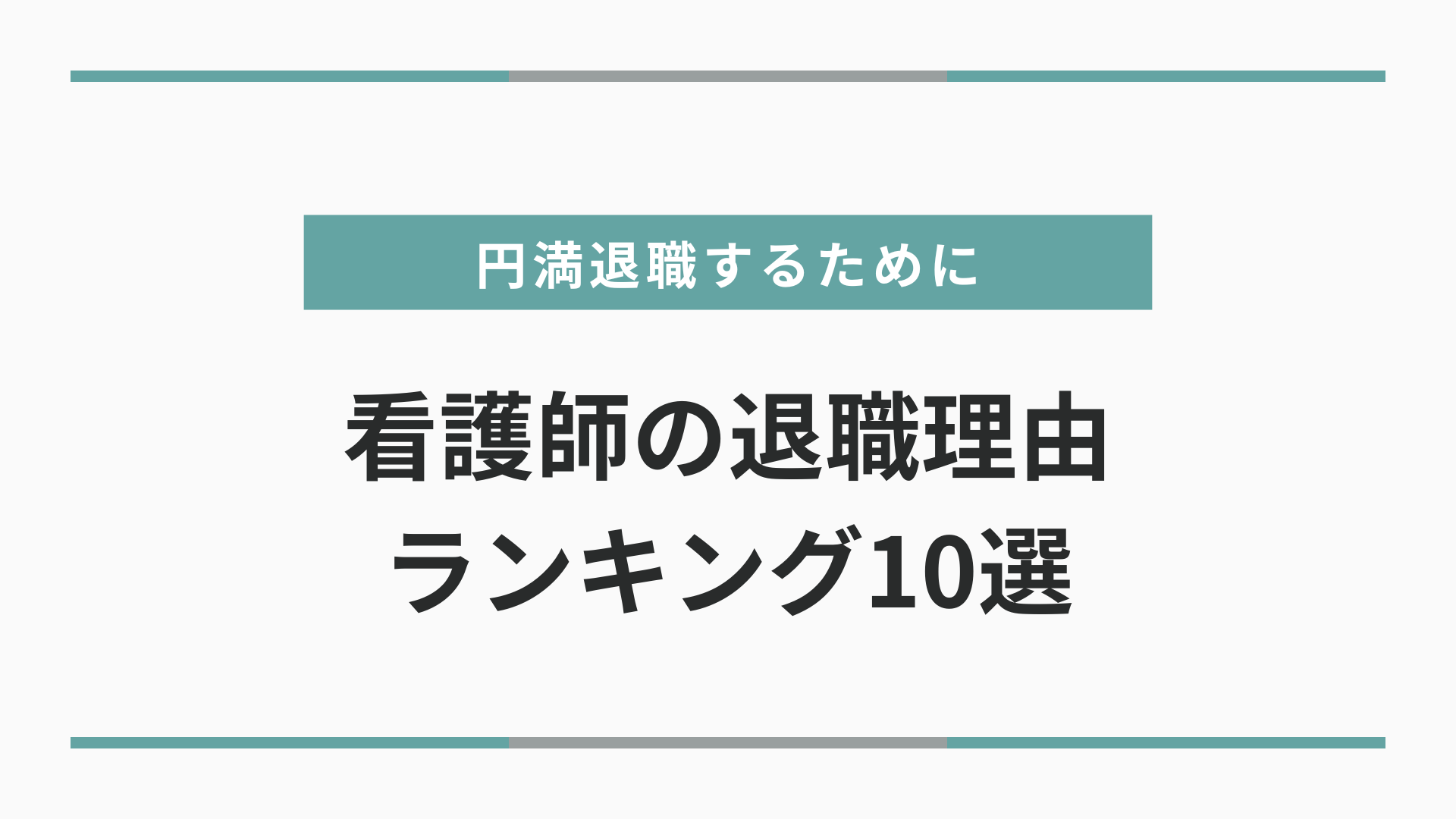
看護師は、患者の命を支える重要な職業です。しかし、離職率が高いのも事実で、多くの看護師が様々な理由で退職を考えています。
「仕事が辛い」「人間関係に疲れた」「給与が低くて割に合わない」といった悩みを抱える人は少なくありません。
看護師が退職を考える背景には、職場環境や労働条件の問題が深く関係しています。しかし、いざ辞めようと思っても「退職の理由はどう伝えたらいいのか?」「辞めることでキャリアに影響はないのか?」と不安になることもあるでしょう。
この記事では、看護師の退職理由をランキング形式で紹介し、円満に退職するための方法について詳しく解説します。
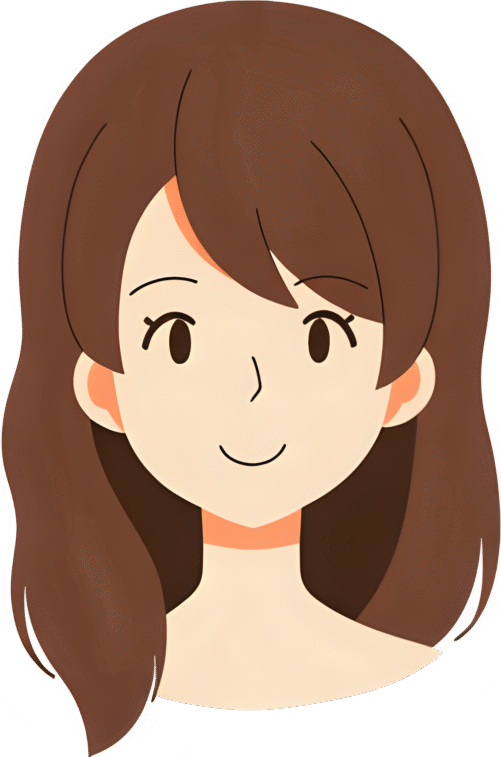
これを読めば、退職を決断する際の判断材料が増え、スムーズな転職やキャリアチェンジにつなげることができます!
看護師が退職を考えるのは珍しいことではない

看護師の退職率は、一般的に高いといわれています。
日本看護協会の2023年病院看護統計調査によると、2022年度の常勤看護師の離職率は11.8%でした。
これは全産業の平均離職率とほぼ同等ですが、新卒看護師の離職率が10.2%、既卒看護師の離職率が16.6%と、経験によって大きな差があることがわかります。
看護師という職業は、人命に関わる大切な仕事であり、高度な専門知識と技術が求められます。
そのため、精神的・肉体的なストレスも大きく、退職を考える看護師も多くいるのでしょう。様々な理由で退職を検討していますが、決して珍しいことではありません。
看護師の退職理由ランキング10選

ここでは、看護師が退職を決意する主な理由をランキング形式で紹介します。
- 人間関係のトラブル(上司・同僚・医師との関係)
- 激務と長時間労働(残業・夜勤の負担)
- 給与が低い・割に合わない
- 精神的なストレス・バーンアウト
- ライフスタイルの変化(結婚・出産・育児・介護)
- 職場の環境・方針が合わない(病院の運営方針・教育制度)
- キャリアアップ・転職希望(スキルアップ・新しい分野への挑戦)
- 体調不良や健康問題(腰痛・過労・メンタルヘルス)
- 患者対応の負担が大きい(クレーム対応)・命の重み)
- 他の業界に興味がある(異業種への転職・独立)
一つずつ詳しく見ていきましょう。
人間関係のトラブル
看護師の退職理由として最も多いのが人間関係の問題です。
病院やクリニックでは、医師、先輩看護師、同僚、患者やその家族との関係によって、仕事を続けられるかどうかが決まります。
しかし、上司からのパワハラ、厳しい指導、同僚との軋轢などが原因でストレスを抱えるケースが後を絶ちません。
特に、新人看護師のうちは「厳しい指導」を受けることが多く、先輩との関係に悩みがちです。「ミスをすると怒鳴られる」「報告や相談がしづらい」といった職場環境では、長く働き続けることが難しくなります。
- 医師
- 先輩看護師
- 同僚
- 患者やその家族
看護師の退職理由として最も多く挙げられるが、特に職場の人間関係です。
病院という特殊な環境下では、上司や同僚との関係だけでなく、医師や他の医療スタッフとの連携によるチーム医療が求められます。
このような現場で、コミュニケーションの齟齬や価値観の違いが生じると大きく、ストレスになってしまいます。
特に新人看護にとっては先輩、看護師や医師とのコミュニケーションに苦労することが多いでしょう。また、患者やその家族との関係で、クレーム対応に疲労してしまう看護師も少なくないのです。
人間関係については、お互いの性格の不一致だけでなく、組織の風土や管理体制にも問題が生じている可能性があります。例えば、パワーハラスメントや過度な競争意識が蔓延している職場では、良い人間関係を築くことが困難になるでしょう。
激務と長時間労働
看護師の勤務はシフト制が多く、夜勤や長時間労働が避けられない職業です。多くの看護師が、この不規則な勤務体制と長時間労働に悩まされているのです。
特に、病棟勤務では夜勤が必須であり、昼夜逆転の生活を強いられます。長時間の立ち仕事や緊張感のある現場での対応が続くため、身体的にも精神的にも疲弊しやすくなります。
さらに、慢性的な人手不足の影響で、一人あたりの業務負担が増加することも問題です。看護師不足が深刻な病院では、一人あたりの業務量が多く、残業が常態化しています。
「休憩時間が取れない」「帰宅が深夜になることが多い」といった状況では、十分な休息が取れずに、心身ともに限界を迎えてしまうことも。
このような激務と長時間労働は、看護師の心身に大きな負担をかけます。慢性的な疲労やストレスの疲労は、バーンアウト(燃え尽き症候群)のリスクを高めるうえに、ワークライフバランスが崩れてしまうことも大きな問題です。
給与が低い・割に合わない
「こんなに大変な仕事なのに、給料が見合っていない」と感じる看護師も多いのが現状です。
看護師の給与は決して低くはありませんが、労働時間や業務量、業務の負担や責任の重さを考えると、割に合わないと感じることがあります。
特に、夜勤手当がない日勤だけの職場では給与が低めになりがちです。また、昇給のスピードが遅い職場では、モチベーションの低下につながることもあります。
このような病院勤務の看護師にとっては、給与面での不満が大きな退職理由となります。
看護師の仕事は、高度な専門知識と技術が要求される上に、人命に関わる重責を担っています。そのため、単純に手当や月給だけでなく、責任の重さや精神的な負担に見合った報酬が求められます。
しかし、多くの医療機関では予算もあり、看護師の期待に応えられていないのが現状です。
また、キャリアアップしても給与が大きく反省しないことも問題です。 経験を積んでも給与面での評価が十分でなければ、より条件の良い職場への転職を考えます。
精神的なストレス・バーンアウト
看護師は、命に関わる現場で働くため、精神的なストレスが大きい職業です。
患者さんの急変や死、家族からのクレーム、医師からのプレッシャーなど、多くの要因が積み重なり、バーンアウト(燃え尽き症候群)になる人もいます。
「夜も眠れないほど悩んでしまう」「仕事のことを考えるだけで憂うつになる」といった状態が続くと、メンタルヘルスに悪影響を及ぼし、退職を決意する要因になります。
看護師の仕事は、常に患者の生命と緊張感と向き合っています。日々の業務におけるプレッシャーや、患者の急変死やそれに耐えることによる精神的ショックは、看護師の心理的負荷を大幅に増加させる要因です。
特に、重症患者や終末期患者のケアに耐える看護師は、強い精神的ストレスにさらされます。また、医療ミスへの不安や責任の重さも、看護師の精神的ストレスの大きな課題となっているでしょう。
このような継続的なストレスや長時間の責任感は、最終的にバーンアウト(燃え尽き症候群)につながることがあり、退職を考えることも少なくありません。
ライフスタイルの変化
結婚や出産、育児、介護など、ライフスタイルの変化に伴って退職を考える看護師も多くいます。特に、夜勤や長時間労働が続く職場では、家庭との両立が難しくなるのです。
- 結婚
- 出産
- 育児
- 介護
- 転勤
「子どもとの時間を大切にしたい」「家庭の事情で夜勤ができない」という理由で、クリニックや訪問看護など、働きやすい職場へ転職する人も増えています。
看護師の多くは女性であり、結婚、出産、育児などのライフイベントが退職理由となることが多い職業でしょう。特に、24時間体制の病院勤務と家庭生活の両立は非常に困難です。
また、出産後の職場復帰を考える際も、夜勤や不規則な勤務時間の壁となります。
保育園の送迎や子どもの急な病気など、予定外の出来事に対応することが難しい職場環境では、育児との両立が難しいと感じる看護師も多いでしょう。
また、結婚や配偶者の転勤に伴う引っ越しも、看護師の退職理由の一つです。さらに、親の介護が必要になるなど、家族の状況の変化も退職を考える大きな課題となります。
看護師自身が介護者となる場合、不規則な勤務との両立はほとんど困難です。
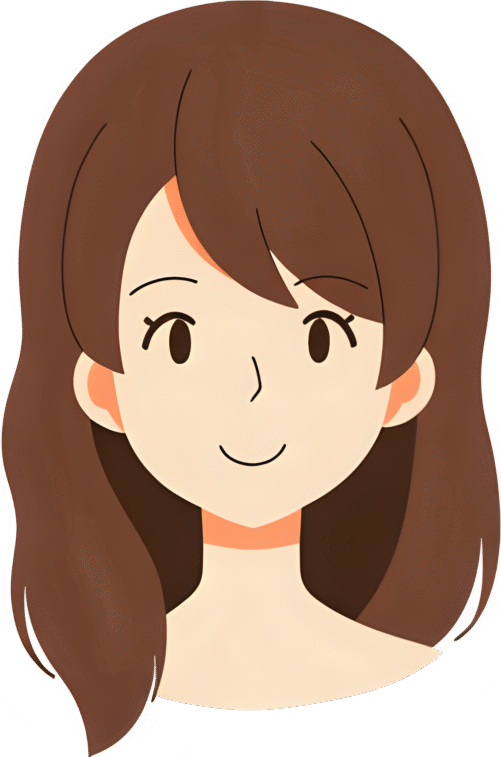
私は、この理由で看護師・保健師の仕事を辞めて、在宅フリーランスになりました!
職場の環境・方針が合わない
病院や医療機関ごとに、その運営方針や職場環境は大きく異なります。自分の価値観や理想とする看護と、職場の方針との違いを感じた場合、退職を考えるきっかけとなることがあるでしょう。
- 自分の看護観と職場の看護方針との違い
- 教育制度や研修体制の不十分さ
- スキルアップの機会がない
- 医療安全や感染対策の方針への疑問
例えば、患者中心の看護を重視したい看護師が、効率や数字を重視する病院で働く場合、大きなストレスを感じることがあります。
新しい医療技術や看護方法の導入に消極的な職場では、自分自身のスキルアップや成長の機会が限られていると感じる看護師も少なくありません。
また、教育制度や研修体制の不足も、看護師の不満につながる課題の一つです。
特に新人看護師にとっては、充実した教育プログラムや上級看護師のサポートが重要です。看護師としての成長に不安を感じ、転職を考えるケースも多いでしょう。
さらに、医療安全に対する取り組みや感染対策の方針など、病院の基本的な姿勢に疑問を感じる場合も、看護師の退職理由となることがあります。
キャリアアップ・転職したい
多くの看護師は、自分のスキルアップやキャリアアップを目指して転職を考えます。
特に、専門性の高い分野に興味を持つ看護師は、その分野でのキャリアを築くために転職を選択することがあります。
- 専門性の高い分野(救急看護、がん看護、小児看護、周産期の看護など)
- 管理職としてのキャリア
また、管理職としてのキャリアを目指す看護師も少なくありません。 ただし、現在の職場で昇進の機会が限られている場合や、管理職としての経験を得るチャンスがない場合は、他の医療機関への転職を考えるでしょう。
さらに、看護師としての経験を踏まえながら、新しい分野に挑戦したいと考える人もいます。他の業界で活躍する道を選ぶ看護師も増えています。
体調不良や健康問題
看護師の仕事は、身体的にも精神的にも非常に負担の大きい職業です。そのため、体調不良や健康問題が原因で退職を考える看護師も少なくありません。
特に多いのが腰痛などの筋骨格系の問題です。
患者の移動や体位変換、長時間の立ち仕事など、看護師の業務には身体的負荷の大きいものが多くあります。慢性的な腰痛や肩こりに悩まされる看護師は多いのです。
また、不規則な勤務体制による睡眠障害も深刻な問題です。夜勤と日勤が交互に続くシフトでは、体内リズムが乱れやすく、慢性的な疲労感や不眠症に悩まされることがあります。
睡眠不足が長期化すると、うつ病などの健康問題につながる可能性もあります。
さらに、医療現場特有のストレスによる心身の不調も消えません。患者の急変や死を目の当たりにすること心理的なショック、感染症のリスクへの不安など、様々なストレスが看護師の健康に影響を与えています。
このような健康問題がしっかりと改善され、日常の業務に影響がなくなれば、退職を考えずに済むこともあるでしょう。看護師自身の健康管理は非常に重要ですが、個人の努力だけでは限界があるため、職場全体でのサポート体制が求められています。
患者対応の負担が大きい
看護師の仕事の中心は患者ケアですが、時として患者やその家族との関係がストレス源となる場合もあります。特に、クレーム対応や大きな要求への対応は、看護師にとって大きな精神的な負担となるでしょう。
患者の中には、病気や入院生活によるストレスから、看護師に対して攻撃的な態度をとる人もいます。これらの困難な状況に日々向き合うことで、看護師は精神的に疲れてしまうことがあります。
また、医療現場のリスクも看護師のストレスを増大させる懸念の一つです。これらの細やかなミスが重大な結果につながる可能性がある医療現場では、常に緊張感を持って患者対応をしなければならず、退職を選択する看護師もいます。
他の業界に興味がある
看護師として働く中で、医療以外の分野に興味を持ち、キャリアチェンジを考える人も少なくありません。看護師としての経験や知識を踏まえて、新しい分野にチャレンジしたいという思いが退職の理由となることがあります。
例えば、医療機器メーカーや製薬会社などの医療関連の企業に転職を考える看護師も多くいます。
これらの企業では、看護師としての臨床経験が製品開発や営業活動に活かせるため、貴重な人材として重宝されます。また、医療系ITベンチャーなどで、電子カルテシステムの開発や医療情報管理の道を選ぶ看護師も増えています。
教育分野でも看護師の経験を活かせるでしょう。学校の看護師や医療系専門学校の講師として、次世代の医療従事者を育成に伝わることで、自分の経験を語りながら新たなやりがいを見つけることができます。
さらに、医療ライターやヘルスケアコンサルタントとして独立する道を選ぶ看護師も増加傾向にあります。医療や健康に関する専門知識を踏まえ、より自由な働き方を求めて転身するケースです。
中には、全く異なる業界にチャレンジする看護師もいます。接客業やサービス業に転職し、人と接する仕事で培ったスキル活かす人もいれば、起業して自分のビジネスを立ち上げる人もいるでしょう。
- 医療機器メーカーや製薬会社
- 医療系ITベンチャー
- 学校や医療系専門学校
- 医療ライターやヘルスケアコンサルタント
- 接客業やサービス業
このように、他の業界に興味を持つ理由は様々ですが、共通しているのは「新しい挑戦への熱い」と「自己実現の欲求」です。
看護師としての経験は、どのような分野でも貴重な財産になります。患者対応で培ったコミニュニケーション能力や、緊急時の冷静な判断力など、看護師の持つスキルは多くの業界で高く評価されるものです。
ただし、業界を変えることは大きな決断であり、リスクもあるため、十分な情報収集と準備が必要です。例えば、転職エージェントに相談したり、興味のある分野でインターンを経験したりするなど、慎重に進路を検討するようにしましょう。
看護師が円満退職するためのポイント
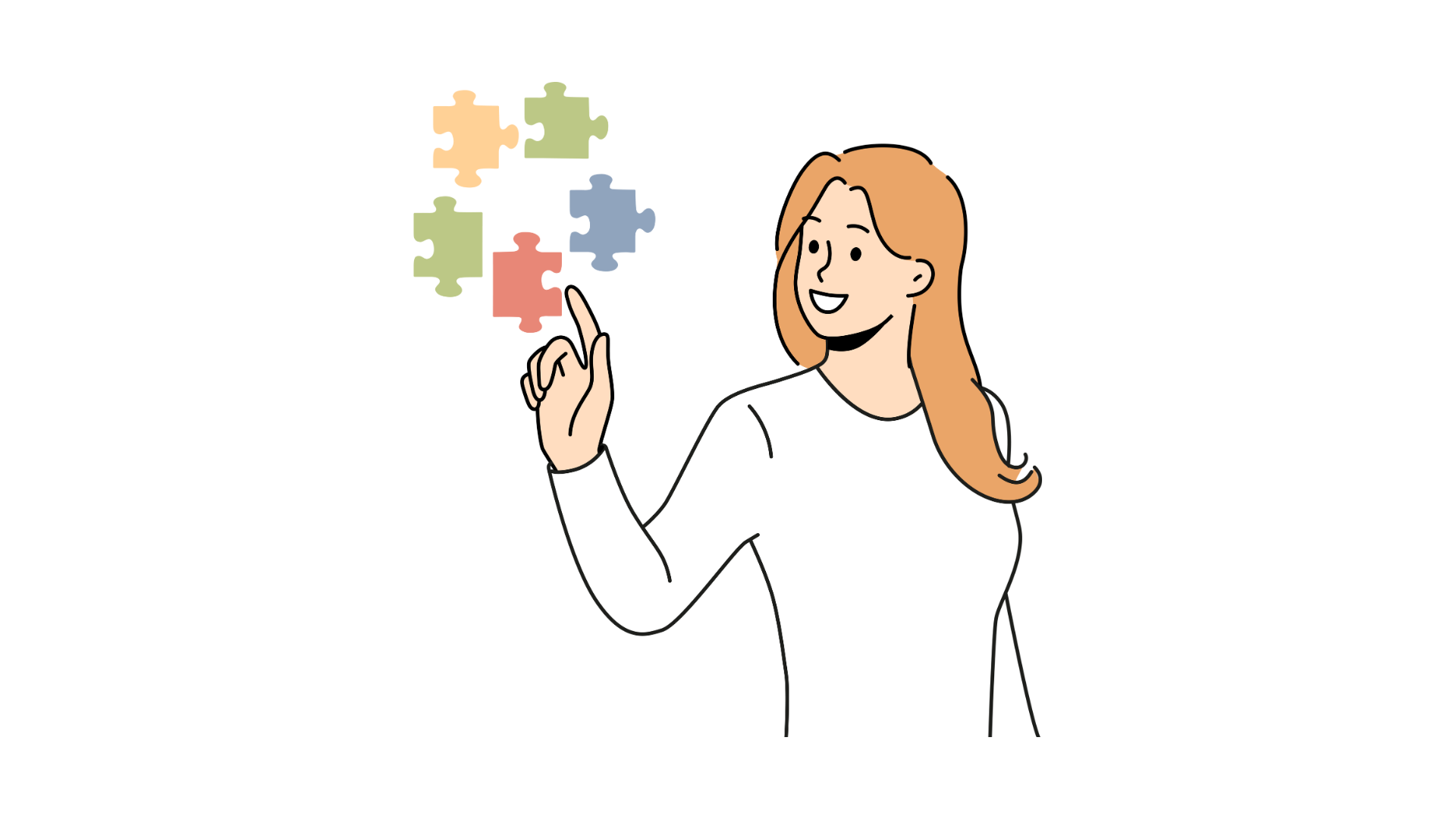
看護師が円満退職するために、4つのポイントを紹介します。
- 退職を決意する前に確認すべきこと
- 退職を伝えるタイミングと伝え方
- 退職願・退職届の書き方
- 引き継ぎをスムーズに進めるコツ
一つずつ詳しく見ていきましょう。
退職を決意する前に確認すべきこと
退職を決意する前に、まずは現在の状況を冷静に分析することが重要です。 退職理由が一時的なストレスや感情的な判断によるものではないか、もう一度確認しましょう。
具体的には以下のような点を確認してみてください。
- 現在の不満や問題点を明確にする
- それらの問題が職場内で解決できないか検討する
- 社長や人事部門と相談し、改善の可能性を探る
- 配置転換や勤務形態の変更など、代替案が確認する
- 退職後のキャリアプランや生活設計を具体的に考える
特に、退職のタイミングについては慎重に検討する必要があります。
例えば、年度途中での退職は病院側職員の配置に大きな影響を与える時期です。また、退職金や有給休暇の取得なども、退職時期によって大きく変わることもあります。
さらに、退職に伴うリスクも考慮しておくべきです。職場が見つかるまでの生活費の問題や、再就職時の条件すべき点は多岐にわたります。
このように、看護師の退職は人生の大きな転機となる決断です。感情的になりすぎず、客観的な視点を持って判断することが重要です。必要に応じて、家族や信頼できる同僚、キャリアカウンセラーなどに相談すると良いでしょう。
退職を伝えるタイミングと伝え方
退職を決意したら、次は正しいタイミングと方法で先に伝える必要があります。これは円満退職のための重要なステップです。
まず、退職を伝えるタイミングについては、一般的に退職希望日の1〜2ヶ月前が正しいとされています。手続きや雇用契約書を確認し、必要な退職予告期間を把握しておきましょう。
退職を伝える際の基本的な流れは以下の通りです。
- 上司と面談を設ける
- 退職の意思を明確に伝える
- 退職理由を考慮して説明する
- 退職希望日を伝える
- 引き継ぎについて相談する
また、伝え方については、以下のポイントに注意しましょう。
- 感情的にならず、冷静に話す
- 感謝の気持ちを忘れずに伝える
- 具体的な退職理由を考えてから説明する
- 相手の反応に配慮しながら会話を進める
- 引き継ぎや残務処理に協力する姿勢を示す
例えば、次のように伝えましょう。
「これまで大変お世話になりました。真剣に考えた結果、私はキャリアアップのために退職を決意しました。○月○日での退職を希望しています。残りの期間、引き継ぎに対応しますので、ご指導よろしくお願いいたします。」
リーダーから引き止めの言葉があった場合も、毅然とした態度を心がけつつ、丁寧に対応することが大切です。
また、退職の話が社内で広まるタイミングにも注意が必要です。 基本的には、上司に伝えた後、人事部門と相談しながら、同僚や部下への報告のタイミングを決めていくのが良いでしょう。
退職を伝える際の対応が、その後の引き継ぎや退職手続きに大きく影響します。丁寧な対応で、円満な退職につなげていきましょう。
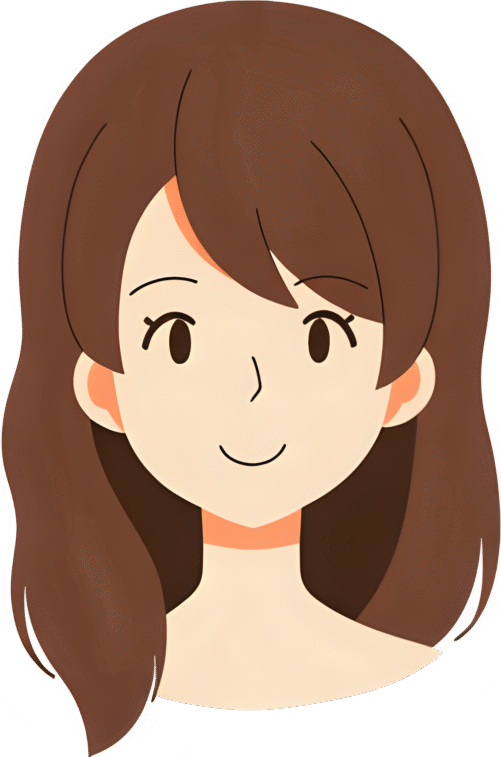
私は、退職するまでに1年かかりました・・余裕を持って退職手続きを進めるべし!
退職願・退職届の書き方
退職の意思を口頭で伝えた後は、正式な書類として退職願または退職届を提出する必要があります。これらの書類は、退職の意思を文書で明確に示すとともに、退職日や引き継ぎなどの具体的なものに関する内容を記録する重要な文書です。
退職願と退職届の違いは以下の通りです。
退職願:退職の許可を求める文書(退職日が確定していない段階で提出)
退職届:退職日が決まった後に提出する正式な通知文書
多くの場合、最初に退職願を提出し、その後退職日が正式に決まったら退職届を提出するという流れになります。
退職願・退職届を作成する際の基本的な記載事項は以下の通りです。
・宛名(病院長や看護部長など)
・表題(「退職願」または「退職届」)
・本文(退職の意思と退職希望日)
・退職理由(簡潔に)
・日付
・氏名(氏名または記名押印)
記載例を以下に記しておきます。
退職願
私儀、このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職致したく、
ここに願い出ます。
長年にわたり賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、
今後ますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
令和○年○月○日
○○病院
看護部長 ○○ ○○ 様
○○科
看護師 ○○ ○○
退職理由については、「身上の都合」や「家庭の事情」などの表現で問題はありません。詳細な理由を記載する必要はありません。
また、文面は丁寧な言葉遣いを心がけ、感謝の気持ちを込めて書くことが大切です。 特に、「今後のご発展を祈ります」といった締めの言葉は忘れずに入れましょう。
ただし、退職願・退職届の提出方法については、病院の規定に従ってください。上長に直接手渡す場合もあれば、人事部門直接提出する場合もあります。
なお、退職願・退職届とは別に、退職に関する詳細な条件(退職金や有給休暇の取得など)について確認が必要な場合は、人事部門と個別に相談するのが一般的です。
正式な書類は丁寧に作成し、適切なタイミングで提出することで、スムーズな退職手続きにつながります。
引き継ぎをスムーズに進めるコツ
円満退職の前には、適切な引き継ぎが必要です。スムーズな引き継ぎは、後任者の負担を軽減するだけでなく、自身の評価にも良い影響を与えます。
以下に、効果的な引き継ぎを行いますそのためのコツをいくつか紹介します。
- 早めの準備開始:退職の意思を伝えたら、すぐに引き継ぎの準備を始める。
- 業務の遂行:日々の業務内容や手順を文書化しておくことが重要。
- 優先順位の明確化:全ての業務を完璧に引き継ぐのは難しい。そのため、重要度や緊急性に応じて業務の優先順位を重視し、効率的に引き継ぎを進める。
- 関係者への挨拶と情報共有:患者さんや他配置との連携が必要な業務については、関係者に退職の挨拶をするとともに、後任者への引き継ぎ状況を伝える。
- 質問しやすい環境づくり:後任者が気軽に質問できる雰囲気を作る。
- 電子データの整理:業務に関連する電子ファイルやメールなどは、わかりやすく整理して引き継ぐ。個人情報や機密情報の取り扱いには十分な注意が必要。
- マニュアルの作成・更新:業務マニュアルがある場合は、最新の情報に更新。マニュアルがない場合は、簡単なものでも良いので作成。
- フォローアップの提案:退職後も一定期間は質問や相談に応じる旨を伝える。
引き継ぎは、自分の仕事に対する責任感と職場への感謝の表れでもあります。
丁寧な引き継ぎを行うことで、良好な人間関係を維持しつつ、気持ちよく退職できます。また、前職での評判は重要な要素となるため、最後まで丁寧に対応することが大切です。
看護師が退職トラブルを避けるための注意点

円満退職を目指して、いくつかのトラブルに注意する必要があります。以下に、よくあるトラブルとその回避方法を紹介します。
- 退職時期の調整
- 機密情報の取り扱い
- SNSでの発言に注意
- 引き抜きの禁止
- 退職金や有給休暇の取り扱い
- 退職理由の一貫性
一つずつ詳しく見ていきましょう。
退職時期の調整
退職のタイミングは、病院の運営に大きな影響を考える可能性があります。
特に、繁忙期や人員が不足している時期の退職は、職場に大きな負担をかけることになるでしょう。上司と相談しながら退職時期を調整することが重要です。
例えば、年末や大型連休前後は避け、比較的落ち着いている時期を選ぶなどの配慮が必要です。
また、後任者の採用や育成にかかる時間も考慮し、十分な引き継ぎ期間を確保できるように、早めに退職の意思を伝えると良いでしょう。
機密情報の取り扱い
医療現場では、患者の個人情報や病院の運営に関する機密情報を日常的に扱います。退職の際には、これらの情報の取り扱いには特に注意が必要です。
退職前に、自分が保有している全ての情報を整理し、個人的に持ち出すことのないよう徹底しましょう。
特に、患者情報が記載された書類やデータは絶対に持ち出してはいけません。
また、業務で使用していたパソコンやスマートフォンなどの電子機器としても、確実に個人情報を削除する必要があります。
SNSでの発言に注意
退職を決意した後や退職後に、SNSで職場の不満や内部情報を発信してしまうケースがあります。
たとえ匿名アカウントであっても、職場や患者に関する情報を公開することは避けましょう。また、退職理由についても詳細を公開することは控えるべきです。
キャリアに悪影響を及ぼす可能性があることを常に意識しておく必要があります。場合によっては、名誉毀損になるリスクもあるので注意しましょう。
引き抜きの禁止
退職後、前の職場の同僚を新しい職場に誘うことは、「引き抜き」として問題になる可能性があります。
特に、管理職や専門性の高い場合には、深刻なトラブルに発展することがあります。
退職時に記載する誓約書などに、一定期間の引き抜き条項が含まれていることも多いため、注意が必要です。
退職金や有給休暇の取り扱い
退職金の計算方法や未消化の有給休暇の取り扱いについて、事前に人事部門とよく確認しておくことが重要です。
退職のタイミングによっては、大きな影響が出る可能性があります。
また、退職前の有給休暇の取得については、職場の状況を考慮しながら計画的に行うべきです。
退職理由の一貫性
社長や人事部門、同僚など、退職理由を説明する相手によって内容を変えてしまうと、後々トラブルの原因になる可能性があります。
特に、否定的な理由を詳細に語ることは避け、前向きな表現を心がけましょう。
例えば、「人間関係の問題」ではなく「キャリアアップのため」といった表現を使うなどの配慮が必要です。
看護師が「退職を言い出しにくい…」そんなときの解決策

退職したいと思っても、なかなか退職の意思を伝えにくい職場環境のケースも多々あります。
とはいえ、我慢してそのまま働き続けるのは、精神衛生上いい状態ではありません。
そのようなときの解決策として、退職の意思を上長に伝えるところから「誰かに任せてしまえ」ばいいのです。このようなサービスを「退職代行サービス」といいます。
退職代行サービスは、最近注目を集めている新しい形の退職支援サービスです。
このサービスを利用することで、直接上長や人事部門と話すことなく、専門家を介して退職手続きを進めることができます。
以下では、退職代行サービスについて、以下の3つのポイントに沿って詳しく解説します。
- 退職代行サービスとは
- 看護師が退職代行を利用するケースが増えている理由
- 退職代行の仕組みと流れ
退職代行サービスとは
多くの看護師が退職を考えながらも、実際に言い出さずに悩んでいる現状があります。 退職代行サービスは、そんな方々にとって大きな助けとなります。
退職代行サービスを利用することで、直接社長に退職の意思を伝える精神的なストレスを軽減できます。特に、人間関係のトラブルが退職理由である場合やパワハラなどの問題がある職場環境では、このサービスは有効です。
また、退職の手続きや交渉を専門家に任せることで、自分自身で対応する場合に比べて、よりスムーズに進めることができます。
退職代行業者は、労働法や退職に関する豊富な知識と経験を持っているため、適切なアドバイスや交渉ができるサービスです。
看護師が退職代行を利用するケースが増えている理由
看護師の間で退職代行サービスの利用が増加している背景には、以下のような理由があります。
- 高ストレス環境:医療現場特有の高ストレス環境から精神的に疲労しているため、直接の対話を避けたい
- 時間的な余裕のなさ:不規則な勤務体制のため、自主退職の手続きを進める時間的な余裕がない
- 専門知識の不足:労働法や退職に関する専門知識が不足している場合、適切な手続きや交渉に不安を感じる
- 客観的な対応:感情的になりがちな退職の場面で、第三者による冷静で客観的な対応を望む
このような背景から、看護師の退職で退職代行サービスを利用したいと考える人が増えているのです。
退職代行の仕組みと流れ
退職代行サービスの基本的な流れは以下の通りです。
- サービス申し込み:オンラインや電話で退職代行サービスに申し込み
- 状況ヒアリング:退職理由や職場の状況、希望する退職日などについての詳細なヒアリング
- 退職交渉:代行業者が雇用主側と連絡をとり、退職の意思を伝え、必要に応じて条件交渉
- 書類作成・提出:退職届などの必要書類の作成と提出を代行
- 退職完了:最終的な退職日の調整や退職金の確認など、退職完了までフォロー
このように、利用者はサービスの担当者に状況を説明して、お任せするだけで退職の意思を伝えるところから、退職完了までを進めることができるのです。
ただし、退職代行サービスを選ぶ際は、注意すべき点があります。以下の通りです。
- 弁護士が関与しているサービスを選ぶ
- 料金体系が明確で、追加料金が発生しにくいサービスを選ぶ
- 看護師や医療従事者の退職に特化したサービスがあれば、それを優先的に検討する
- 利用者の評判や口コミを確認する
退職代行サービスは、正しく利用することで、看護師のスムーズな退職と次のキャリアへの前向きな一歩を支援する有効な手段となります。
「退職が難しい…」と感じたら、退職代行サービスを活用しよう!

看護師の退職理由は多岐にわたり、出産・育児、結婚、他分野への興味、人間関係の問題、長時間労働などが挙げられます。そのため、看護師が退職を考えるのは珍しいことではありません。
まずは、円満退職のために、適切な時期の選択、十分な引き継ぎ期間の確保、丁寧な退職の伝え方を理解しましょう。
退職を伝える際は、就業規則の確認、上長への事前相談、退職日の調整、退職届の提出、業務引き継ぎ、挨拶など、段階的なプロセスを踏むことが大切です。
また、退職後のキャリアについても十分に検討し、自分の目標や生活スタイルに合った選択をしましょう。
退職は看護師にとって大きな決断ですが、適切な準備と対応により、円満に次のステップへ進むことができます。
Wrote this article この記事を書いた人
あゆ
元ナース・保健師のあゆ。 元看護師・保健師で、転職5回を経て現在はフリーランスとして活動中! 看護師として働く中で、悩み続けて1年かけて退職した経験があります。その過程で、退職を切り出す難しさや、退職後のキャリアへの不安を痛感しました。 『ナースの退職お悩み相談室』では、退職を考える看護師の方々に役立つ情報や、退職代行サービスの活用法、退職後のキャリアプランなどを発信しています。皆さんが一歩踏み出すお手伝いができれば嬉しいです。