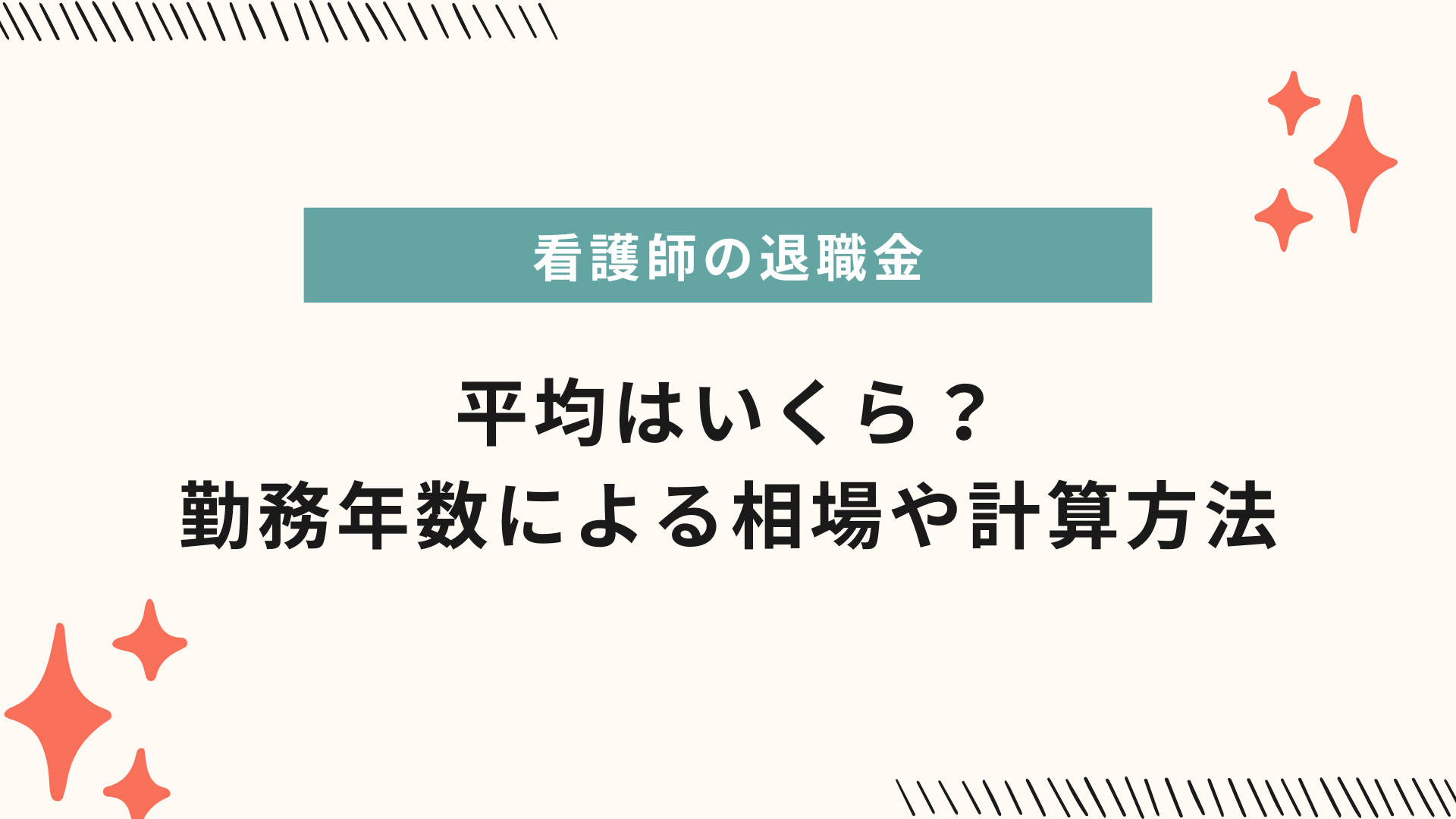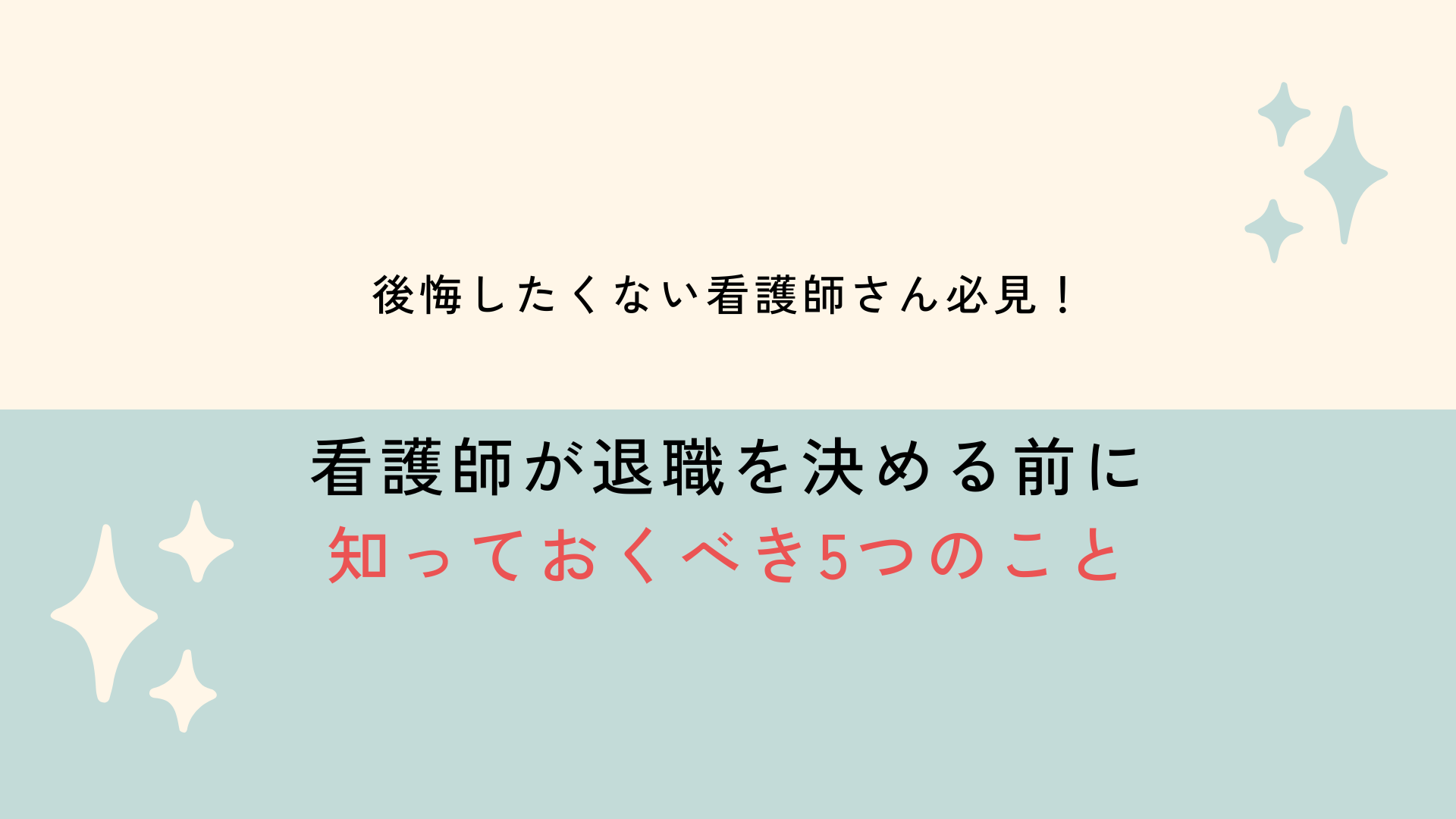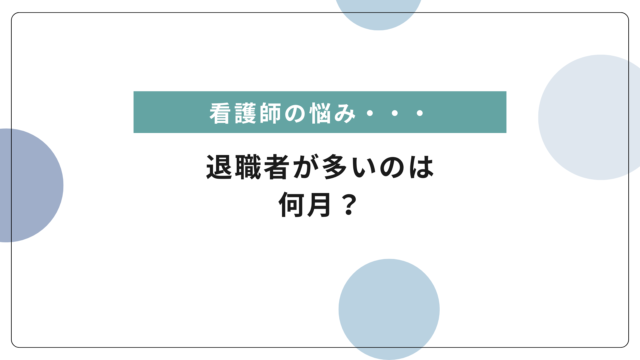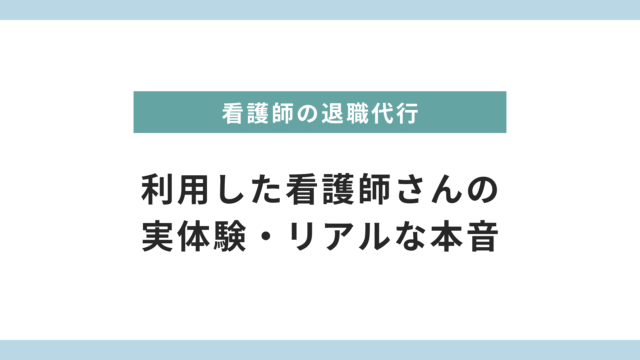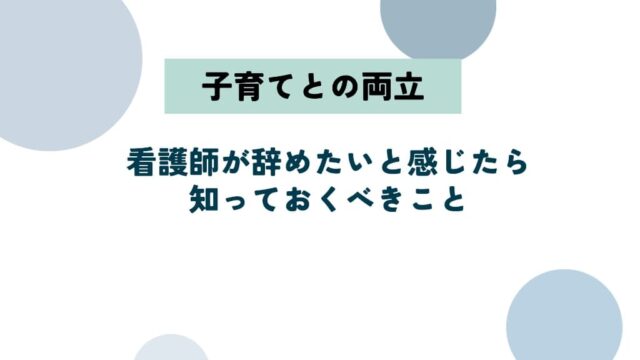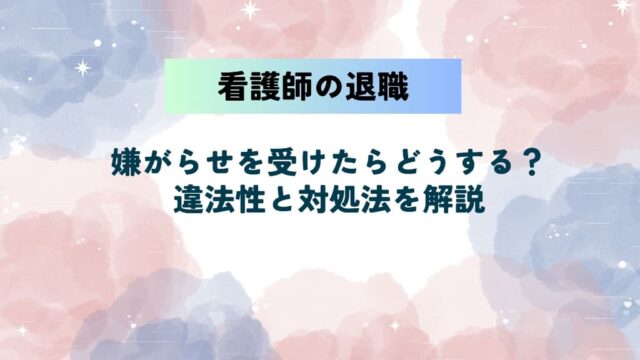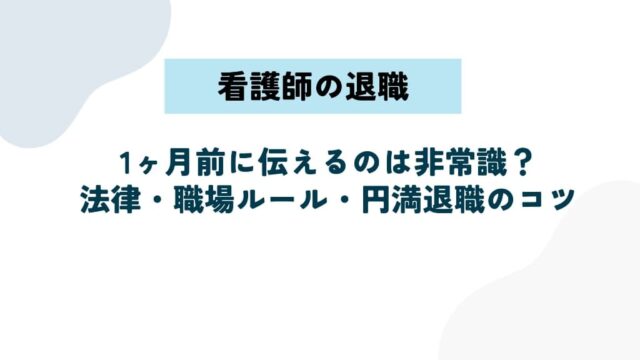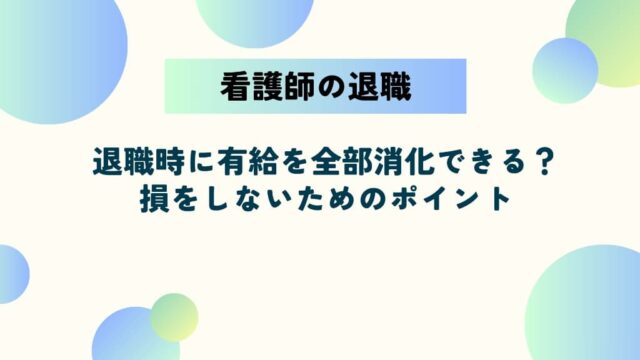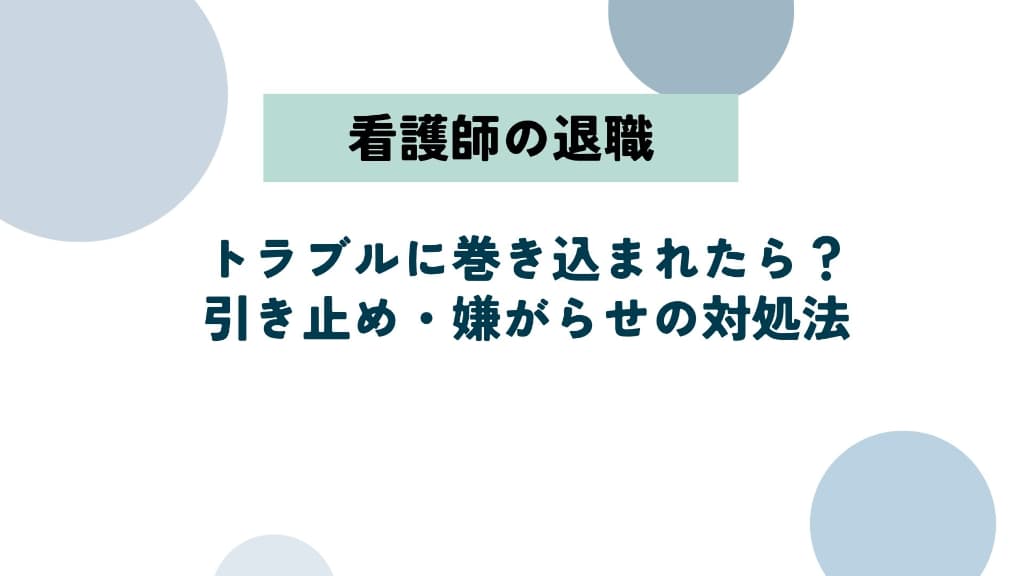
看護師の退職でトラブルが起きることは珍しくありません。「退職を申し出たら強く引き止められた」「上司から嫌がらせを受けている」「退職願を受理してもらえない」といった悩みを抱えている方も多いでしょう。
看護師は責任の重い職業だからこそ、退職時にトラブルが発生しやすい環境があります。しかし、退職は労働者の正当な権利です。
この記事では、看護師の退職でよくあるトラブル例と具体的な対処法、そして円満退職のためのポイントを詳しく解説します。
あなたの心身と将来を守るために、適切な知識と対策を身につけて、冷静に退職を進めていきましょう。
看護師の退職、なぜトラブルが多いの?
看護師の退職時にトラブルが発生しやすいのには、医療現場特有の事情があります。まずは、なぜトラブルが起きやすいのかを理解しておきましょう。
人手不足・慢性的な現場の負担
日本の医療現場は慢性的な看護師不足に悩まされています。厚生労働省の調査によると、看護師の有効求人倍率は2倍を超えており、どの医療機関でも人材確保に苦労している状況です。
このような状況下では、一人の看護師が退職することの影響が非常に大きくなります。
管理者側としては「なんとしても引き止めたい」という心理が働き、時として強引な引き止めや感情的な対応につながってしまうことがあります。
また、現場の看護師たちも常に業務に追われているため、退職者に対して「みんな頑張っているのに」「負担が増える」といった感情を抱きやすく、それがプレッシャーや嫌がらせにつながることもあります。
看護師業界ならではの人間関係
看護の現場は女性が多い職場であり、独特な人間関係が形成されがちです。長年勤務している先輩看護師の発言力が強く、新しい意見や変化を受け入れにくい雰囲気がある職場も少なくありません。
また、「患者さんのために」「チームのために」という名目で、個人の意思よりも集団の利益が優先される文化があります。これ自体は悪いことではありませんが、時として個人の退職という正当な権利まで抑制してしまうことがあります。
さらに、医療現場では「責任感」や「使命感」が強く求められるため、退職を申し出ること自体が「無責任」「逃げ」と捉えられがちです。
このような価値観が、退職時のトラブルを生む土壌となっています。
引き止めや嫌がらせが起きやすい理由
看護師の退職で引き止めや嫌がらせが起きやすい背景には、以下のような要因があります。
まず、看護師の教育には時間とコストがかかるため、管理者側は投資した人材を失いたくないという思いが強くなります。特に専門性の高い部署や、指導的立場にある看護師の場合、その傾向は顕著です。
また、シフト制の勤務体制では、一人が抜けることで他のメンバーの負担が直接的に増加します。このため、同僚からの圧力や不満の声が上がりやすく、それが退職者へのプレッシャーとなることがあります。
さらに、一部の管理者は「退職は個人の甘え」「もっと我慢すべき」といった古い価値観を持っており、退職者に対して感情的な対応をしてしまうケースもあります。
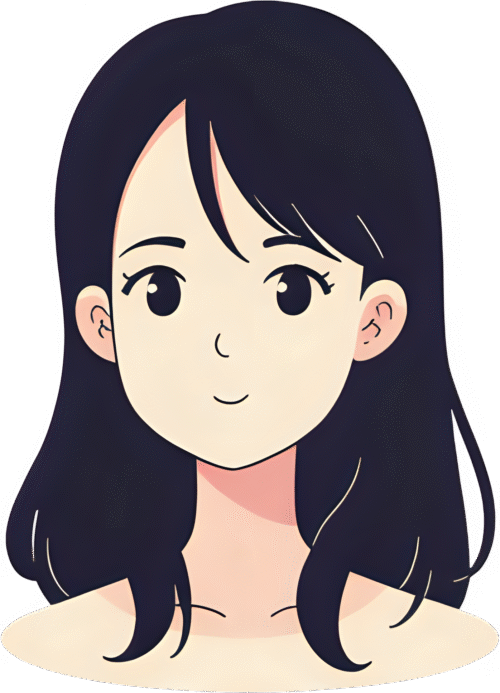
私が最初に退職を考えた時、「みんな我慢して働いているのに、あなただけ逃げるつもり?」という無言の圧力を感じました。
退職は個人の権利なのに、なぜか罪悪感を感じさせられてしまう職場の雰囲気がありました。
よくある退職トラブル例と対処法
看護師の退職で実際に起こりがちなトラブルと、それぞれの対処法を具体的に見ていきましょう。
強引な引き止めにあう
最も多いトラブルが、上司からの強引な引き止めです。「あなたがいないと困る」「患者さんはどうなるの?」「もう少し頑張れないの?」といった感情的な言葉で退職を思いとどまらせようとするケースです。
このような引き止めに対しては、まず退職の意思が固いことを明確に伝えることが重要です。以下のように、具体的な日付とともにはっきりと伝えましょう。
- 「よく考えた結果の決断です」
- 「○月○日での退職をお願いします」
また、引き止めの理由に対して感情的に反論するのではなく、「引き継ぎはしっかりと行います」「可能な限り協力します」といった建設的な姿勢を示すことで、相手の理解を得やすくなります。
条件改善の提案(給与アップ、部署異動、勤務時間の調整など)があった場合は、一度検討する時間をもらい、冷静に判断しましょう。
ただし、根本的な問題が解決されない限り、同じ悩みが再発する可能性があることも考慮が必要です。
退職理由を否定・詮索される
「そんな理由で辞めるなんて」「もっと詳しく聞かせて」といった形で、退職理由を詮索されたり否定されたりするケースもあります。
退職理由については、「一身上の都合」で十分です。
詳細を話す義務はありませんし、プライベートな事情まで説明する必要もありません。相手が詮索してきても、「個人的な事情なので」「一身上の都合ということで理解していただきたい」と答えれば問題ありません。
もし退職理由を否定された場合は、「ご意見はありがたいですが、決断は変わりません」と冷静に対応しましょう。
相手の意見に左右されず、自分の判断を信じることが大切です。
退職までの間、嫌がらせ・無視をされる
退職を申し出た後、以下のように、職場で嫌がらせや無視を受けるケースもあります。
- 業務の情報を教えてもらえない
- 必要以上に厳しく当たられる
- 同僚から避けられる
このような場合は、まず記録を残すことが重要です。
いつ、誰から、どのような嫌がらせを受けたかを詳細に記録しておきましょう。証拠があることで、後々の対応がしやすくなります。
業務に支障が出るような嫌がらせについては、直属の上司や人事部門に相談しましょう。「退職までの期間、円滑に業務を行いたい」という姿勢を示し、協力を求めることが大切です。
精神的な負担が大きい場合は、労働基準監督署や看護協会の相談窓口に連絡することも検討しましょう。職場でのハラスメントは決して許されることではありません。
嫌がらせの対策については、「看護師が退職時に嫌がらせを受けたらどうする?違法性と対処法を解説」も参考にしてみてください。
退職願を受理してもらえない・話し合いが進まない
退職願を提出しても「受け取れない」「もう少し考えて」と言われ、手続きが進まないケースもあります。
退職願を受理してもらえない場合は、まず就業規則を確認しましょう。退職の申し出期限や手続き方法が明記されているはずです。規則に従って適切に手続きを行っていることを明確にしましょう。
それでも受理されない場合は、退職願のコピーを取り、配達証明付きの郵便で人事部門や病院長宛に送付する方法もあります。これにより、確実に退職の意思を伝達し、記録も残すことができます。
法律上、労働者は2週間前に退職の意思表示をすれば退職できるため、最終的には法的な手続きに移ることも可能です。
退職を言い出すの時期の違いについては【退職は何ヶ月前が正解?1・2・3ヶ月前の違いは?】も参考にしてみてください。
有給消化を認めてもらえない
退職前の有給消化を認めてもらえない、または嫌な顔をされるといったトラブルもよくあります。しかし、有給休暇の取得は労働者の権利であり、退職時であっても原則として拒否することはできません。
有給消化を申請する際は、業務の引き継ぎスケジュールと合わせて計画的に提出しましょう。
「○月○日から○日まで有給を取得し、引き継ぎは○日までに完了予定です」といった具体的な提案をすることで、理解を得やすくなります。
それでも認めてもらえない場合は、就業規則を確認し、有給休暇の取得条件を確認しましょう。正当な理由なく有給取得を拒否することは、労働基準法違反にあたる可能性があります。
関連記事:看護師は退職時に有給を全部消化できる?損をしないためのポイント
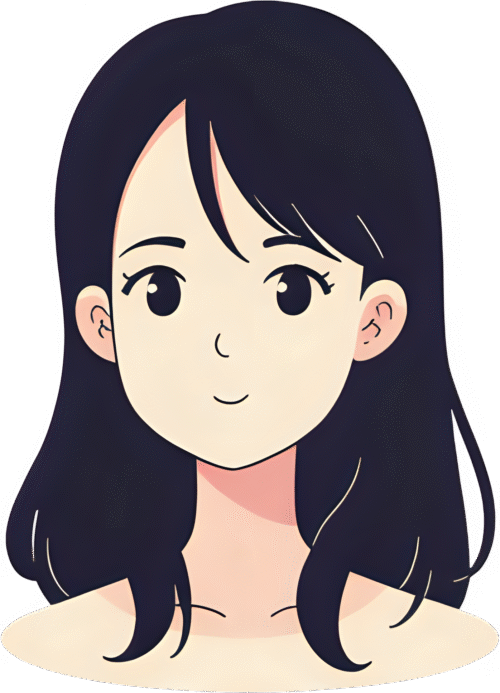
最初の職場で退職が決まっていた最後の1ヶ月。師長から「ごめんなさいね。」という言葉と共に最後の勤務表が渡されました。
見ると、退職日当日までぎっしり勤務が詰まっており、希望していた有給が1日も取れていませんでした・・・!
当時は知識がなくて諦めてしまい、非常にもったいないことをしたなと思っています。
トラブルを防ぐ!退職を伝える時のポイント
退職時のトラブルを防ぐためには、最初の伝え方が非常に重要です。以下のポイントを押さえて、スムーズな退職を目指しましょう。
タイミングと伝え方が大事
退職を伝えるタイミングは、就業規則に従うことが基本です。一般的には1〜3ヶ月前の申し出が求められますが、できるだけ早めに相談することで、トラブルを避けやすくなります。
繁忙期や人手不足が深刻な時期は避け、比較的落ち着いているタイミングを選びましょう。また、朝の忙しい時間や業務終了間際ではなく、上司がゆっくり話を聞ける時間帯に相談することも大切です。
伝え方については、まず「ご相談があります」という形で時間を取ってもらい、落ち着いた環境で話すことが重要です。
メールやLINEでの突然の退職報告は避け、必ず対面で伝えるようにしましょう。
「一身上の都合」で十分、詳細は言わなくてOK
退職理由については、「一身上の都合」という表現で十分です。詳細な事情を説明する必要はありませんし、プライベートな内容まで話す義務もありません。
「なぜ辞めるのか詳しく聞かせて」と言われても、「個人的な事情で」「家庭の都合で」といった表現にとどめることができます。具体的な理由を話すことで、それを否定されたり、反論されたりするリスクが高まります。
ただし、前向きな理由(キャリアアップ、結婚、転居など)であれば、簡潔に説明することで理解を得やすくなる場合もあります。状況に応じて判断しましょう。
退職の意思はハッキリ伝える
退職の意思を伝える際は、曖昧な表現は避け、明確に伝えることが重要です。「○月○日付けで退職させていただきたいと思います」とはっきり伝えましょう。
また、「検討していただけませんか」「お願いします」といった相談の形ではなく、「退職いたします」という確定的な表現を使うことで、意思の強さを示すことができます。
曖昧な表現は相手に期待を持たせてしまい、後々のトラブルの原因となる可能性があります。一度伝えた後は、ブレずに一貫した姿勢を保つことが大切です。
事前に必要な情報(就業規則・退職手続き)を確認する
退職を申し出る前に、就業規則や退職手続きについて確認しておきましょう。退職の申し出期限、必要な書類、引き継ぎ期間など、基本的な情報を把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。
また、有給休暇の残日数や退職金の支給条件なども事前に確認しておくと良いでしょう。これらの情報があることで、退職交渉の際に具体的な話し合いができます。
就業規則が確認できない場合は、人事部門に問い合わせるか、労働基準監督署で相談することも可能です。知識があることで、不当な要求に対しても適切に対応できるようになります。
退職時の手続きについて知りたい方は【退職時にやるべき手続きと書類・退職理由別の注意点】も参考にしてみてください。
もしトラブルになった場合の具体的対応法
万が一退職時にトラブルが発生した場合の対処法を知っておくことで、冷静に対応することができます。
感情的にならず冷静に対応する
退職時にトラブルが発生すると、つい感情的になってしまいがちですが、冷静な対応を心がけることが最も重要です。相手が感情的になっても、こちらは落ち着いて対応することで、状況の悪化を防ぐことができます。
「お気持ちは理解いたします」「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」といった共感の言葉を使いながら、自分の立場を説明しましょう。相手を否定するのではなく、自分の事情を理解してもらう姿勢が大切です。
また、一度の話し合いで解決しない場合は、時間を置いて再度話し合いの機会を設けることも有効です。お互いが冷静になることで、建設的な話し合いができる場合があります。
退職の切り出し方に悩む方は【看護師の退職の切り出し方5ステップ】を活用してみてくださいね。
記録を残す(やり取りのメモ・メール)
退職に関するやり取りは、必ず記録を残しておきましょう。日時、相手、話した内容、約束事項などを詳細にメモしておくことで、後々のトラブル防止につながります。
可能であれば、重要な話し合いの後はメールで内容を確認することも有効です。「本日の件について確認させていただきます。○月○日付けでの退職について、お話しいただいた内容は以下の通りでよろしいでしょうか」といった形で、書面に残すことができます。
録音については、相手の同意なく行うと問題になる場合があるため、慎重に判断する必要があります。ただし、パワハラなどの証拠として必要な場合は、法的な相談をした上で検討することも可能です。
必要なら第三者(労基・看護協会など)に相談する
職場内での話し合いで解決しない場合は、第三者機関への相談を検討しましょう。以下のような相談窓口があります。
- 労働基準監督署
労働基準法違反や職場でのハラスメントについて相談できます。退職の妨害、有給休暇の拒否、不当な処遇などについて指導を受けることができます。 - 都道府県看護協会
看護師特有の悩みについて相談できます。同じ看護師の立場から適切なアドバイスを受けることができるでしょう。 - 労働局の総合労働相談コーナー
労働問題全般について無料で相談できます。専門の相談員が対応してくれるため、具体的な解決策を提案してもらえます。
これらの機関に相談する際は、これまでの経緯を整理し、記録したメモや書類を持参すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。
精神的に限界なら、退職代行の活用も選択肢
職場でのトラブルが深刻で、精神的な負担が大きい場合は、退職代行サービスの利用も選択肢の一つです。退職代行サービスでは、本人に代わって退職の手続きを行ってくれるため、直接的な対立を避けることができます。
退職代行には、一般企業が運営するものと弁護士が運営するものがあります。弁護士運営の場合は、法的なトラブルにも対応できるため、より安心して利用できます。
費用は3〜5万円程度が相場ですが、精神的な負担や時間的コストを考えると、有効な選択肢と言えるでしょう。ただし、同じ地域で再就職を考えている場合は、評判への影響も考慮する必要があります。
退職代行について知りたい方は【看護師向け退職代行サービスおすすめランキング】を読んでみてくださいね。
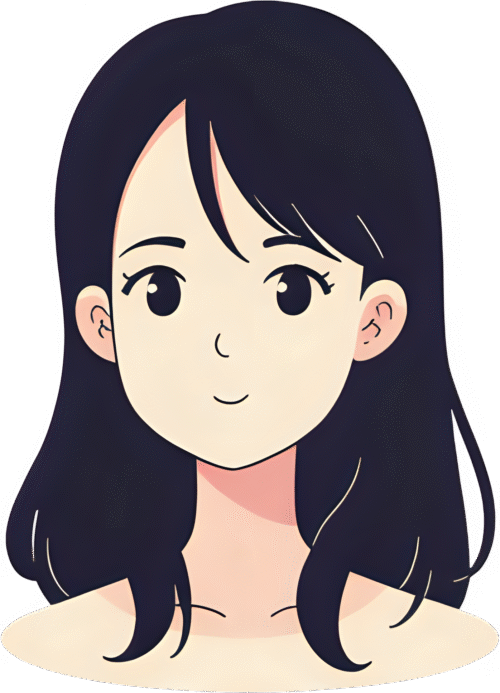
私は気が弱いので、面と向かって病院と戦う勇気はありません。
我慢しすぎて心身を壊してしまうくらいなら、プロのサポートを受けることも大切です!
まとめ|自分を大切に、冷静に退職を進めよう
看護師の退職時にトラブルが発生することは珍しくありませんが、適切な知識と対応方法を知っておくことで、多くのトラブルは回避できます。
また、万が一トラブルが発生しても、冷静に対処することで解決への道筋を見つけることができるでしょう。
まず大切なのは、退職は労働者の正当な権利であり、無理して我慢する必要はないということです。「患者さんのため」「職場のため」という理由で個人の権利が制限されることはありません。
あなたの健康と将来を最優先に考えて判断してください。
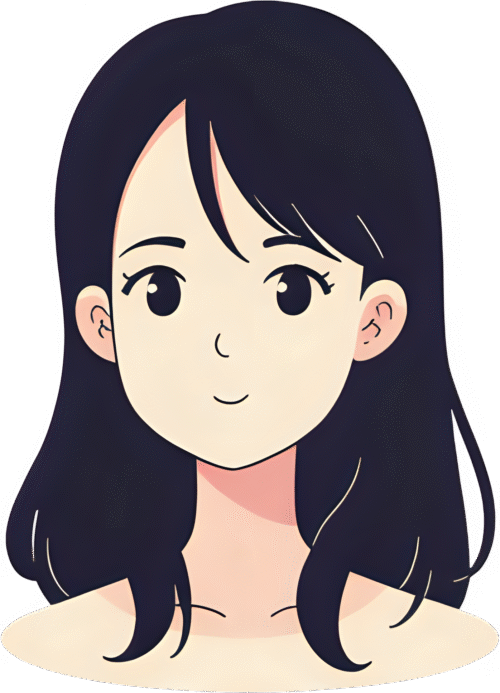
一人で悩みを抱え込まずに、適切なサポートを受けながら前に進んでくださいね!
\ 次に読みたい記事はこちら /
▼退職を決める前に知っておきたい退職金の仕組み
看護師の退職金の平均はいくら?5年・10年・定年など勤務年数による相場や計算方法を解説
▼奨学金の一括返済を考える場合
看護師の奨学金が理由で退職できない?一括返済とお礼奉公のリアルな乗り越え方
▼退職時の強い引き止め対策に
受理されない・強い引き止めにあったらどうする?円満に断る方法を解説
▼退職を決断する前の最終チェックリスト
【後悔したくない人必見】看護師が退職を決める前に知っておくべき5つのこと
Wrote this article この記事を書いた人
ぽー
看護師・保健師・養護教諭資格あり。 転職経験は3回で、現在はフリーランスとして活動中です。急性期から退院支援、外来などさまざまな部署で看護の仕事をしてきました。 子育てと仕事との両立に悩み、ライフステージの変化に応じて働き方を変えていった経緯があります。 働き方に悩む看護師が、より自分らしく働くために役立つ情報を発信していきます。